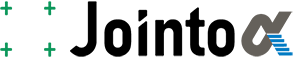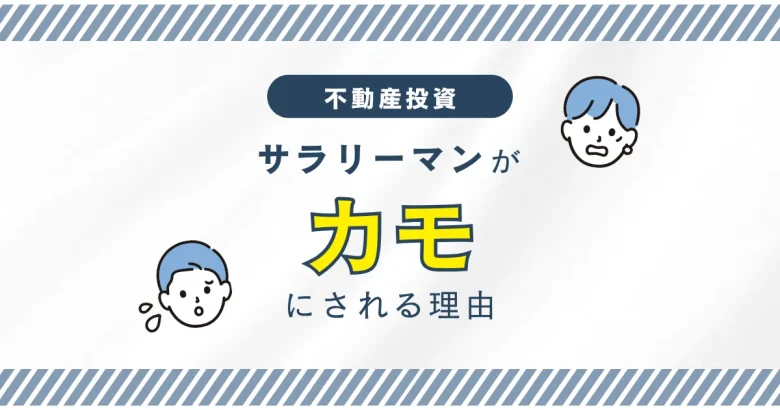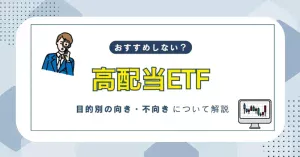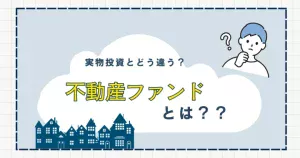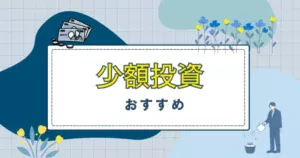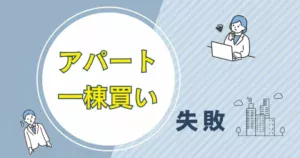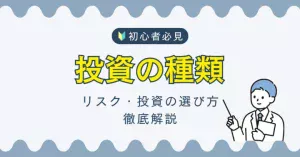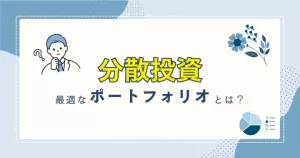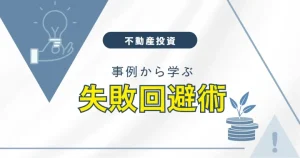サラリーマンには、安定した収入があるという大きな強みがあります。この安定性により銀行のローン審査に通りやすく、不動産投資を始めやすい環境にあるといえるでしょう。
しかし、その一方で悪徳な不動産会社にとって「カモ」にされやすい存在でもあります。安定収入があることで高額な物件を購入させられたり、不利な条件の契約を結ばされたりするケースが後を絶ちません。
自分自身で不動産投資の仕組みやリスクをしっかりと理解すれば、このような被害を避けて安定した利益を得ることができます。今回は、カモにならずに済む方法や、サラリーマンが不動産投資を成功させるために意識すべきポイントなどを詳しく解説していきます。
- サラリーマンが悪質な不動産投資のカモにされやすい理由とその手口
- 不動産投資でカモにされやすいサラリーマンの特徴
- 不動産投資で成功するために意識すべきポイント
サラリーマンが悪徳な不動産投資のカモになりやすい理由

サラリーマンが不動産投資で狙われやすいのには、明確な理由があります。悪徳業者はサラリーマンの特徴を熟知しており、その弱点を巧みに突いてきます。まずは、なぜサラリーマンがターゲットにされやすいのかを理解しましょう。
収入が安定しているか
サラリーマンが狙われる最大の理由は、毎月決まった給料をもらっているからです。この安定収入により、銀行から高額なローンを組みやすい状況にあります。
悪徳業者はこの点に目をつけ、「あなたなら問題なくローンが通ります」と甘い言葉をかけてきます。実際に金融機関もサラリーマンの安定した収入を評価するため、自己資金が少なくても数千万円の物件を購入できてしまうのです。
しかし、ローンが通ることと投資が成功することはまったく別の話です。毎月の返済額が家賃収入を上回ってしまい、持ち出しが発生するケースも珍しくありません。安定収入があるからこそ、慎重な判断が必要なのです。
不動産投資の専門的な知識を持っている人が少ないから
普段の仕事が不動産とは無関係な分野で働くサラリーマンは、不動産投資に関する深い知識を持っていない場合が多いと想定されます。
この知識不足を悪徳業者は巧みに利用します。専門用語を並べて説明し、あたかも非常に有利な投資であるかのように見せかけるのです。例えば、「表面利回り10%」という数字だけを強調し、実際の収支がマイナスになる可能性については詳しく説明しません。
また、不動産投資にはさまざまなリスクが伴いますが、これらについても十分な説明を行わないケースも少なくありません。空室リスクや修繕費用、管理費などの説明が不十分なまま契約を進められてしまいます。
節税メリットを魅力的に感じてしまうから
サラリーマンにとって、節税は魅力的に感じられます。特に年収が高い人ほど、税負担を軽減したいという思いが強くなります。
悪徳業者はこの心理を利用し、「不動産投資で大幅に節税できます」とうたい文句にします。確かに不動産投資では減価償却費(建物の価値が年々下がることを費用として計上する会計処理)などにより、一時的に節税効果を得られる場合があります。
しかし、節税効果だけを目的とした投資は本末転倒です。節税により数十万円を節約できても、投資自体で数百万円の損失を出してしまっては意味がありません。節税はあくまで副次的なメリットとして考えるべきなのです。
不動産投資のカモにされやすいサラリーマンの特徴

悪徳業者にカモにされやすいサラリーマンには、共通した特徴があります。これらの特徴に当てはまる人は特に注意が必要です。自分自身を客観視し、危険なパターンに陥らないよう気を付けましょう。
自分で不動産投資について学ぶ意欲がない
もっとも危険なのは、自分で勉強せずに不動産会社の言うことをうのみにしてしまう人です。「不動産投資は難しそうだから、プロに任せておけば大丈夫」という考えは非常に危険といわざるを得ません。
投資は自己責任が原則です。どんなに信頼できそうな不動産会社でも、最終的に損失を被るのは投資家本人です。書籍やインターネット、セミナーなどで基礎知識を身に付けることは最低限必要でしょう。
特に不動産投資の基本的な仕組み、収益構造、リスクについては必ず理解しておくべきです。これらの知識があれば、明らかに不利な条件の提案を見抜くことができます。
メリットを過大評価してデメリットをきちんと理解しない
不動産投資にはメリットもデメリットも存在します。しかし、カモにされやすい人は不動産会社が強調するメリットばかりに注目し、デメリットやリスクを軽視してしまいます。
例えば、「家賃収入で老後の安心を得られます」という説明を聞いて、そのとおりになると思い込んでしまうのです。実際には空室期間があったり、修繕費用がかかったりして、思ったような収入を得られないことも多々あります。
投資判断を行う際は、最悪のケースも想定して検討することが大切です。「もし空室が続いたら」「もし大規模修繕が必要になったら」といったリスクシナリオも考慮に入れましょう。
「不労所得」「楽して稼げる」という甘言に弱い
「不動産投資は不労所得です」「何もしなくてもお金が入ってきます」といった甘い言葉に引かれてしまう人も要注意です。実際の不動産投資は決して楽な投資ではありません。
物件の管理や入居者対応、修繕の手配など、さまざまな業務が発生します。管理会社に委託することも可能ですが、その分コストがかかり収益性は下がります。また、委託したとしても、オーナーとしての判断が必要な場面は多く存在します。
本当の意味での不労所得を期待するのではなく、ある程度の労力をかけて運営していく事業として捉える必要があります。不動産投資は、「事業の一つ」として捉えて、リスクを取る必要がある点に留意しなければなりません。
物件の調査やリスクの想定を自分で行わない
優良な投資物件を見つけるためには、入念な調査が欠かせません。しかし、カモにされやすい人は不動産会社の説明だけを信じて、自分では何も調べようとしません。
立地条件・周辺環境・賃貸需要・競合物件の状況など、調べるべき項目は多岐にわたります。写真や資料だけでは分からない情報がたくさんあるため、実際に現地を見に行くことも重要です。
また、将来的に起こり得るリスクについても想定しなければなりません。人口減少や駅前の再開発、競合物件の建設など、収益に影響を与える要因は数多く存在します。
「節税」「生命保険の代わり」の意味をきちんと理解しない
悪徳業者がよく使ううたい文句に「節税効果があります」「生命保険の代わりになります」というものがあります。これらの言葉の真の意味を理解せずに、安易に契約してしまう人が多いのです。
節税については先ほども触れましたが、一時的な効果に過ぎない場合がほとんどです。減価償却が終われば節税効果はなくなり、むしろ税負担が増えることもあります。
「生命保険の代わり」というのは、ローンに団体信用生命保険(ローン契約者が死亡した場合にローン残債が免除される保険)が付いているからです。しかし、団信はローンの残債がなくなる効果はあるものの、通常の生命保険のように遺族へまとまったお金を渡せるものではありません。
不動産投資でカモにされたサラリーマンの事例

実際に、サラリーマンが悪徳業者にカモにされてしまった事例を見てみましょう。これらのパターンを知っておくことで、同じような被害を避けることができます。
新築ワンルームマンションをローンで購入させられる
もっとも多い被害事例が、新築ワンルームマンションの押し売りです。不動産会社は「都心の新築物件なので資産価値が下がりません」「家賃保証があるので安心です」など、甘言を用いて説明してきます。
しかし、新築ワンルームマンションは購入価格が高く設定されているため、家賃収入だけではローン返済をカバーできないケースがほとんどです。毎月数万円の持ち出しが発生し、長期間にわたって負担が続きます。
また、新築プレミアムにより購入直後から物件価値が大幅に下落するため、売却しようとしてもローン残債を下回る価格でしか売れません。結果として、多額の損失を抱えることになってしまいます。
サブリース契約を締結させられる
サブリース契約とは、不動産会社が物件を一括で借り上げ、オーナーに一定の家賃を保証する仕組みです。不動産会社は「空室リスクがありません」「管理の手間も不要です」と魅力的な説明をします。
しかし、サブリース契約には大きな落とし穴があります。契約書をよく読むと、家賃は定期的に見直されることになっており、実際に市場家賃が下落すれば保証家賃も下げられてしまいます。
また、契約解除の条件が非常に厳しく設定されており、オーナーが不利な状況に置かれることが多いのです。さらに、サブリース会社が倒産してしまうリスクもあります。
大規模修繕が必要な物件を購入させられる
築年数が古い物件を「利回りが高い」という理由で購入させ、その後高額な修繕費用を請求するパターンもあります。不動産会社は修繕の必要性について十分な説明を行わず、購入後に問題が発覚します。
外壁の塗装や屋根の補修、給排水設備の交換など、大規模修繕には数百万円の費用がかかることもあります。これらの費用を事前に想定していないと、突然の出費に困る事態になりかねません。
さらに悪質なケースでは、不動産会社の関連会社に修繕を依頼するよう誘導し、相場よりも高額な工事費用を請求してきます。他社と比較検討する機会を与えず、「緊急性がある」などと理由をつけて契約をせかすのが典型的な手口です。
サラリーマンが不動産投資を始めるときに意識すべきポイント
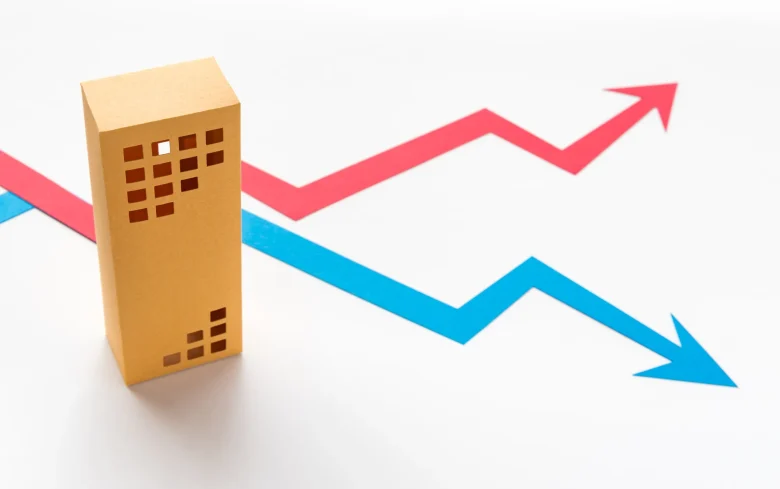
ここまで失敗事例を見てきましたが、適切な知識と準備があれば、サラリーマンでも不動産投資で成功することは十分可能です。以下のポイントを意識して取り組めば、リスクを最小限に抑えながら安定した収益を得ることができるでしょう。
不動産投資のリスクを必ず理解する
不動産投資を始める前に、どのようなリスクがあるのかを必ず理解しておきましょう。主なリスクには以下のようなものがあります。
| 空室リスク | 入居者が見つからない、または退去により家賃収入が途絶えるリスク |
| 家賃下落リスク | 築年数の経過や周辺環境の変化により、設定可能な家賃が下落するリスク |
| 家賃滞納リスク | 入居者が家賃を支払わないリスク |
| 入居者トラブル | 騒音、ペット、ゴミ出し等のトラブルにより近隣住民やほかの入居者に影響するリスク |
| 大規模修繕リスク | 外壁塗装、屋根補修、配管交換など高額な修繕費用が突発的に発生するリスク |
| 設備故障リスク | エアコン、給湯器、エレベーターなどの設備故障による修理・交換費用が発生するリスク |
| 自然災害リスク | 地震、台風、洪水、火災などによる建物が損傷するリスク |
| 建物老朽化リスク | 経年劣化により建物の資産価値が低下し、賃貸需要も減少するリスク |
| 金利上昇リスク | 変動金利での借入時、金利上昇により返済額が増加し収益性が悪化するリスク |
| インフレリスク | 物価上昇により建材費や人件費が高騰し、修繕・管理コストが増加するリスク |
| 不動産価格下落リスク | 経済情勢悪化や不動産市況低迷により物件価格が下落するリスク |
| 法規制変更リスク | 建築基準法、消防法、賃貸住宅管理業法等の法改正により追加コストが発生するリスク |
| 税制変更リスク | 不動産取得税、固定資産税、所得税等の税制変更により税負担が増加するリスク |
| 人口減少リスク | 地域人口の減少により賃貸需要が縮小し、空室率上昇・家賃下落につながるリスク |
| 競合物件増加リスク | 近隣への新築物件建設により賃貸需給バランスが崩れ、空室率上昇・家賃下落につながるリスク |
| 管理会社リスク | 委託した管理会社の倒産、管理品質が低下するリスク |
| 流動性リスク | 急にお金が必要になっても不動産は簡単に現金化できないリスク |
| 環境変化リスク | 近隣に嫌悪施設建設、治安悪化による環境変化リスク |
不動産投資にはさまざまなリスクが伴い、リスクをゼロにすることはできません。これらのリスクを理解した上で、どのように対策を取るかを事前に考えておくことが重要です。
また、それぞれのリスクが実際に起こった場合、どの程度の影響が出るのかも考える必要があります。投資を始めた後、環境の変化が起きても冷静に対処するためにも、リスクを織り込んで収益をシミュレーションすることは大切です。
「表面利回り」ではなく「実質利回り」を見る
物件の収益性を判断する際は、表面利回りではなく実質利回りを重視しましょう。
- 表面利回りとは…
-
表面利回りは、年間家賃収入を物件価格で割った数字です。
例えば…3000万円の物件で年間家賃収入が300万円なら、表面利回りは10%となります。
- 実質利回りとは…
-
実質利回りは、年間家賃収入から諸経費を差し引いた実質的な収入を物件価格で割った数字です。諸経費には管理費・修繕積立金・固定資産税・管理会社への手数料・火災保険料などが含まれます。
例えば…上記の物件で年間諸経費が60万円かかる場合、
実質利回りは(300万円-60万円)÷3000万円=8%となります。
実質利回りが重要な理由は、実際の手取り収入が分かるからです。実質利回りは年間家賃収入から諸経費を差し引いた「実際の手取り収入」で計算するため、現実的な収益を把握できます。
例えば表面利回り8%の物件でも、諸経費が年間家賃収入の30%かかれば、実質利回りは約5.6%まで下がります。この差を知らずに投資すると、期待していた収益が得られません。
表面利回りが同じ2つの物件でも、管理費や修繕費の違いで実質利回りに大きな差が出ることがあります。実質利回りで比較することで、本当に収益性の高い物件を選べます。さらに正確な収益性を把握するためには、空室期間も考慮した実質利回りを計算するとよいでしょう。
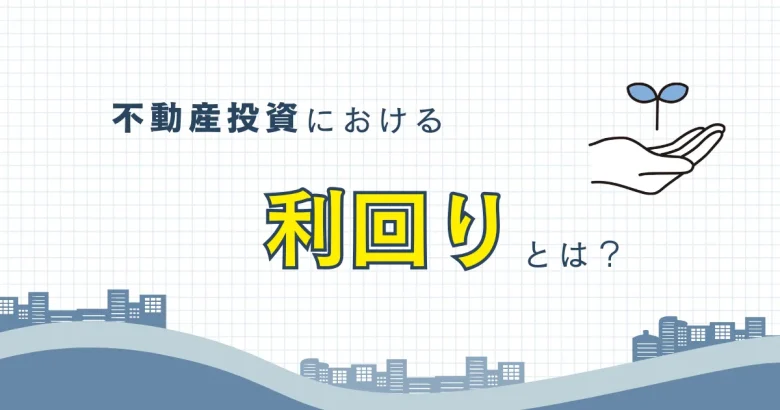
疑問点や不明点を放置しない
不動産投資の検討過程で疑問点や不明点が出てきたら、必ず確認して解消しましょう。分からないことをそのままにして契約を進めるのは、非常に危険です。
不動産会社に質問をして、納得できる説明が得られない場合は、その会社との取引は見送るべきです。優良で信頼できる不動産会社であれば、顧客の疑問に対して丁寧で分かりやすい説明をしてくれるはずです。
また、契約書の内容についても十分に確認しましょう。専門用語が多くて理解しにくい場合は、不動産に詳しい第三者や専門家に相談することをおすすめします。
「今すぐ決めないとほかの人に取られてしまう」などとせかされても、冷静に判断する時間を取ることが大切です。本当によい物件であれば、じっくり検討する時間があっても問題ないはずです。
信頼できる不動産会社で相談する
不動産投資を成功させるためには、信頼できるパートナーとなる不動産会社を見つけることが重要です。
まず、宅地建物取引業の免許を持っているかを確認します。免許番号の記載があり、国土交通省や都道府県のホームページで不動産会社の情報を確認できます。
次に、実績や専門性を確認しましょう。不動産投資を専門的に扱っている会社のほうが、適切なアドバイスを受けられる可能性が高いです。
また、強引な営業をしてこない不動産会社を選ぶことも大切です。顧客の立場に立って、メリットだけでなくリスクについても正直に説明してくれる会社が信頼できます。
複数の不動産会社と相談し、提案内容や対応を比較検討することをおすすめします。一社だけの意見をうのみにせず、セカンドオピニオンを求めることも重要です。
不動産投資の先輩に話を聞く
実際に不動産投資を行っている先輩投資家から話を聞くことで、リアルな情報を得ることができます。書籍やセミナーでは学べない実体験に基づくアドバイスは、これから投資を始める方にとって参考になるはずです。
不動産投資の勉強会やセミナー、オンラインコミュニティなどで先輩投資家と交流する機会をつくりましょう。成功体験だけでなく、失敗体験も聞かせてもらうことで、より現実的な視点を持つことができます。
ただし、投資は人それぞれ状況が異なるため、他人の成功事例をそのまままねすればよいというわけではありません。あくまで参考情報として活用し、最終的には自分自身で判断することが大切です。
また、特定の物件や業者を強く勧めてくる人には注意が必要です。紹介料目的である可能性もあるため、複数の意見を聞いて冷静に判断しましょう。
資金計画をきちんと立てる
不動産投資を始める前に、詳細な資金計画を立てることが重要です。初期費用やランニングコスト、将来の修繕費用などを含めた総合的な計画を作成しましょう。
不動産投資を始めるにあたって、必要になる初期費用は以下のとおりです。
- 物件価格
- 仲介手数料
- 登記費用
- 不動産取得税
- 火災保険料
- ローン事務手数料 など
続いて、ランニングコストです。
- ローン返済額
- 管理費
- 修繕積立金
- 固定資産税
- 管理会社への手数料
- 火災保険料 など
これらの費用は、収入を得られているかどうかに関係なく発生し続けます。家賃収入で賄えるかどうか、空室が発生しても支払えるかを必ず確認しましょう。
将来に発生する費用として、大規模修繕費用や空室時の収入減少なども想定しておく必要があります。築年数に応じて必要となる修繕の時期と費用を事前に調べておきましょう。
また、不動産投資用の資金と生活資金は明確に分けて管理することが大切です。生活に必要な資金まで投資に回してしまうと、万が一の際に生活が困窮してしまいます。
投資する物件の調査は入念に行う
物件選びは、不動産投資の成否を左右するもっとも重要な要素です。不動産会社の説明だけに頼らず、自分自身で入念な調査を行いましょう。文字情報だけでなく、実際に自分の目で確認しましょう。
立地条件の調査では、最寄り駅からの距離や周辺の商業施設、学校・病院などの利便性を確認します。また、将来的な開発予定や人口動態の変化についても調べておきましょう。
物件の状態については、築年数・構造・付帯設備の状況を詳しく確認します。可能であれば、建物診断を受けることをおすすめします。外観だけでなく、配管や電気設備の状況も重要なチェックポイントです。
賃貸需要を調べるために、周辺の類似物件の家賃相場や空室状況を調査しましょう。不動産ポータルサイトで類似物件を検索すれば、大まかな相場を把握できます。
競合物件の状況も重要です。近隣に新築物件の建設予定がないか、類似物件が供給過多になっていないかを確認しましょう。供給過多の状況だと、家賃の下落圧力がかかり、収益を損ねてしまう可能性があるためです。
また、実際に複数回にわたって現地を訪れることをおすすめします。昼間と夜間、平日と休日など、異なる時間帯の様子を観察することも大切です。
まずは少額から始める
不動産投資の初心者は、いきなり高額な物件に手を出すのではなく、まずは少額から始めることをおすすめします。小さく始めることで、リスクを抑えながら経験を積むことができます。
例えば、地方の築古アパートや区分マンションなど、数百万円程度の物件から始めてみましょう。これらの物件であれば、たとえ失敗しても致命的な損失を避けることができます。
少額投資で経験を積み、不動産投資の仕組みやリスクを実体験として理解できれば、その後により大きな投資を検討することも可能になります。
また、一つの物件に集中投資するのではなく、複数の物件に分散投資することでリスクを分散することも重要です。地域や物件タイプを変えることで、特定のリスクの影響を軽減できます。
投資規模を徐々に拡大していく際も、常に自分の資力の範囲内で行うことが大切です。借入額が過大になると、わずかな収益悪化でも返済に困る状況に陥ってしまいます。
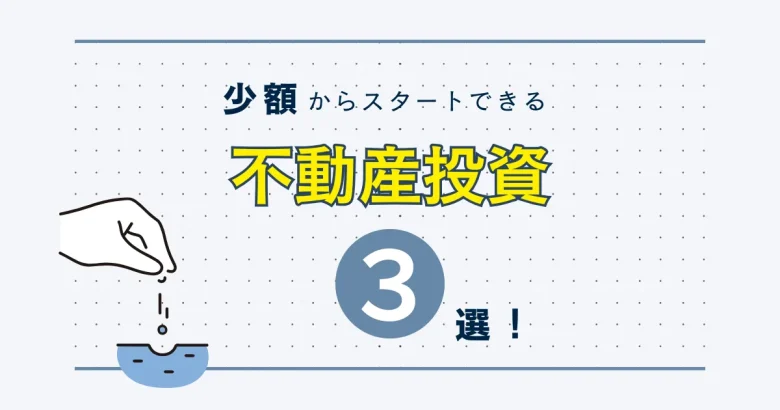
少額から不動産投資を始めるなら不動産クラウドファンディングがおすすめ

不動産投資に興味はあるものの、いきなり物件を購入するのはハードルが高いと感じる方には、不動産クラウドファンディングという選択肢があります。これは比較的新しい投資手法で、少額から不動産投資を体験できる仕組みです。
不動産クラウドファンディングとは、複数の投資家から資金を集めて不動産を取得し、その収益を投資家に分配する仕組みです。1万円程度の少額から投資可能で、物件の管理や運営はすべて運営会社が行います。
この仕組みの最大のメリットは、少額から始められることです。通常の不動産投資では数百万円以上の資金が必要ですが、クラウドファンディングなら数万円から投資を始められます。
また、物件の管理や入居者対応などの手間が一切かからないのも大きな魅力です。投資家は資金を出すだけで、後の運営はすべて運営会社に任せることができます。
さらに、運営会社が厳選した物件に投資できるため、個人では投資しにくい優良物件にアクセスできる可能性があります。商業施設やオフィスビルなど、個人投資家では手の届かない物件への投資も可能です。
不動産クラウドファンディングは、不動産投資の入門編として、まず少額で体験してみたい方に適した投資手法といえるでしょう。実際の不動産投資の感覚をつかんでから、将来的に現物不動産投資にステップアップすることも可能です。
まとめ
サラリーマンが不動産投資でカモにされやすいのは、安定収入があることで高額なローンを組みやすいからです。専門知識が不足しがちで、節税メリットなどの甘い言葉に惑わされやすい方は注意が必要です。
悪徳業者は、学習意欲がなく、リスクを軽視し、「楽して稼げる」という考えを持つサラリーマンを狙ってきます。新築ワンルームマンションの押し売りやサブリース契約、修繕費用の水増しなど、さまざまな手口で被害を与えています。
しかし、適切な知識と準備があれば、サラリーマンでも不動産投資で成功することは十分可能です。まずはリスクをしっかりと理解し、表面利回りではなく実質利回りを重視しましょう。
疑問点は必ず解消し、信頼できる不動産会社を選び、先輩投資家からアドバイスを受けることも大切です。また、自分自身でも不動産投資に関する勉強をして、リスク要因やリスクへの対策を考えましょう。
よくある質問

【監修】

穴吹興産株式会社 不動産ソリューション事業部
アセットマネジメントグループ課長 穴吹 章彦
【資格】
・宅地建物取引士
・不動産証券化協会認定マスター
【経歴】
ソリューション事業部の業務に7年従事し、投資用不動産のアセットマネジメント業務を経験。現在は不動産特定共同事業におけるファンドの組成業務に従事し、投資家との契約業務全般を担当。不動産クラウドファンディングの仕組みや専門用語を解説しながら、情報発信を行っている。