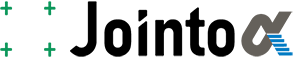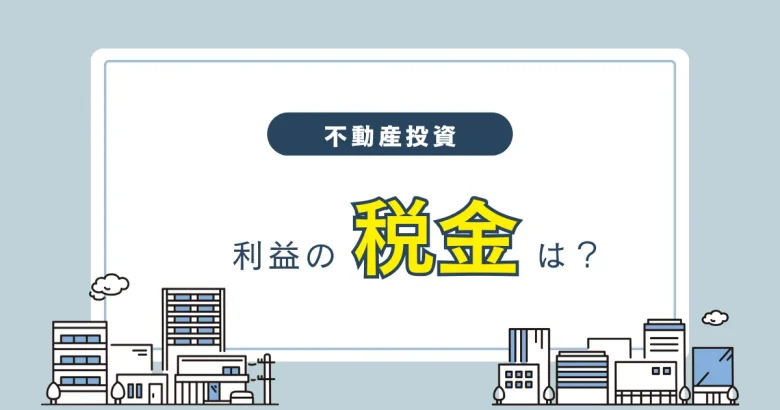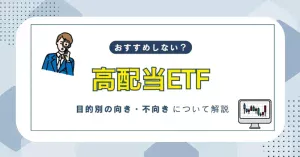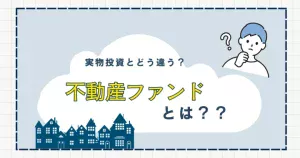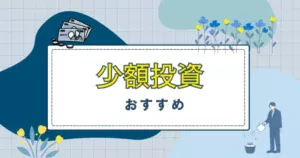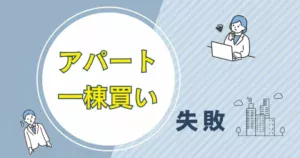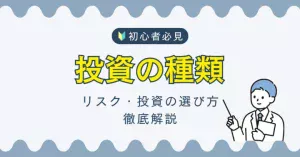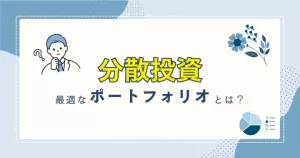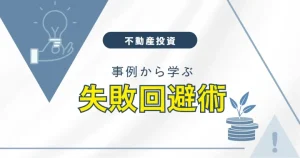不動産投資を始める際に気になるのが、税金の負担でしょう。物件を購入してから売却するまで、さまざまなタイミングで異なる種類の税金がかかります。
この記事では、不動産投資にかかるすべての税金を詳しく解説し、効果的な節税方法も紹介します。初心者の方でも分かりやすいよう、専門用語には丁寧な説明を加えていますので、ぜひ最後までお読みください。
・投資用不動産の購入時・運用時・売却時にそれぞれ発生する税金について
・所得税と住民税のシュミレーション
・税負担を軽減する方法について
投資用不動産の購入時に発生する税金

不動産を購入する際には、複数の税金を支払う必要があります。これらの税金は物件価格とは別に準備しておかなければならないため、資金計画を立てる上で重要な要素となります。
購入時の税金は主に4種類あり、それぞれ計算方法や支払いタイミングが異なります。事前に把握しておくことで、予想外の出費を避けられるでしょう。
不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物を取得した際に都道府県が課税する地方税です。購入後3カ月から6カ月程度で納税通知書が届き、一括または分割で支払います。
税率は原則として固定資産税評価額の4%ですが、住宅用の土地・建物については3%の軽減税率が適用されています。また、新築住宅の場合は1,200万円、新築家屋が「認定長期優良住宅」の場合は1,300万円を控除できます。
例えば、固定資産税評価額が2,000万円のマンションを購入した場合、通常なら60万円(2,000万円×3%)の不動産取得税がかかります。しかし、新築住宅の控除を利用すれば24万円((2,000万円-1,200万円)×3%)まで軽減可能です。
印紙税
印紙税は、不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書(ローン契約書)に貼付する収入印紙代として支払う国税です。契約金額に応じて税額が決まり、契約書作成時に現金で支払います。
令和9年3月31日までの間に作成される不動産の売買契約に関する印紙税は、以下のとおりです。
| 記載された契約金額 | 税額 |
|---|---|
| 10万円を超え50万円以下 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 1万円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 16万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 32万円 |
| 50億円を超える | 48万円 |
登録免許税
登録免許税は、不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記を行う際に法務局に納める国税です。登記申請時に収入印紙や現金で支払い、登記完了と同時に所有権が正式に移転されます。

所有権移転登記の税率は、土地が・建物ともに固定資産税評価額の2%です。
消費税
消費税は、建物部分の購入代金にかかる間接税です。土地には消費税がかからないため、建物と土地を区分して計算する必要があります。
個人が住宅用の中古マンションを購入する場合、売主が個人であれば消費税はかかりません。しかし、売主が不動産会社などの事業者の場合は10%の消費税が発生します。
また、不動産会社への仲介手数料や司法書士への報酬、火災保険料なども消費税の課税対象となるため、これらの費用も含めて資金計画を立てましょう。
投資用不動産の運用時に発生する税金


不動産投資では、物件を保有している期間中も継続的に税金が発生します。これらの税金は毎年または毎月の支払いとなるため、キャッシュフローを計算する際に重要な要素です。
運用時の税金は主に4種類あり、それぞれ計算基準や支払い方法が異なります。
固定資産税・都市計画税
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課税される市町村税です。都市計画税は、市街化区域内の土地・建物に課税される目的税で、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられます。
固定資産税の税率は1.4%、都市計画税の税率は最高0.3%です。ただし、住宅用地については軽減措置があり、200平方メートル以下の小規模住宅用地は固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1に軽減されます。
固定資産税評価額が土地2,000万円、建物1,500万円の投資用マンションの場合、年間の固定資産税・都市計画税は約35万円程度になります。これを毎月の家賃収入から差し引いて収益を計算する必要があります。
所得税
所得税は、不動産投資で得た家賃収入から必要経費を差し引いた不動産所得に対してかかる国税です。ほかの所得と合算して総合課税方式で計算され、所得金額に応じて5%から45%の累進税率が適用されます。
不動産所得の計算では、家賃収入から管理費・修繕費・減価償却費・借入金利息・固定資産税などの必要経費を差し引きます。
年収500万円のサラリーマンが年間300万円の家賃収入を得て、必要経費が200万円だった場合、不動産所得は100万円となります。この場合、所得税率は20%程度となり、不動産所得に対しては約20万円の所得税がかかります。
住民税
住民税は、前年の所得に対して翌年度に課税される地方税です。都道府県民税と市町村民税を合わせて住民税と呼び、税率は原則として一律10%(都道府県民税4%、市町村民税6%)となっています。
不動産所得がある場合、給与所得と合算した総所得金額に対して住民税が計算されます。所得税と同様に、必要経費をしっかりと計上することで住民税の軽減も可能です。
さきほどの例では、不動産所得100万円に対して約10万円の住民税がかかります。所得税と合わせると合計30万円程度の税負担となるため、事前に資金を準備しておく必要があります。
個人事業税
個人事業税は、不動産投資の規模が一定以上になった場合に課税される都道府県税です。アパートやマンションなどの建物を10室以上、または土地を駐車場として50台分以上貸し付けている場合に事業として認定され、課税対象となります。
税率は業種によって異なりますが、不動産貸付業の場合は5%です。ただし、事業的規模でない場合や、年間の事業所得が290万円以下の場合は課税されません。
例えば、15室のアパートを経営して年間の不動産所得が500万円ある場合、290万円を超える210万円に対して5%の個人事業税がかかります。この場合、年額10.5万円の納税が必要です。
投資用不動産の売却時に発生する税金


不動産を売却する際には、売却益に対する税金と手続きに関する税金が発生します。特に売却益(譲渡所得)にかかる税金は高額になるケースが多いため、事前の計画が重要です。
譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産を売却して利益が出た場合にかかる国税です。売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得に対して課税され、保有期間によって税率が大きく異なります。
保有期間が5年以下の短期譲渡所得の場合は30%、5年超の長期譲渡所得の場合は15%の税率が適用されます。保有期間は売却した年の1月1日時点で判定するため、実際の保有期間とは異なる場合があります。
3,000万円で購入した物件を5年後に4,000万円で売却し、譲渡費用が200万円だった場合、譲渡所得は800万円となります。長期譲渡所得として15%の税率が適用され、120万円の譲渡所得税がかかります。
住民税
住民税は、譲渡所得に対して都道府県民税と市町村民税が課税される地方税です。譲渡所得税と同様に、保有期間によって税率が変わります。
短期譲渡所得の場合は9%(都道府県民税2%、市町村民税7%)、長期譲渡所得の場合は5%(都道府県民税2%、市町村民税3%)の税率が適用されます。
上記の例では、長期譲渡所得800万円に対して5%の住民税がかかり、40万円の納税が必要です。譲渡所得税と合わせると合計160万円の税負担となります。
印紙税
売却時の印紙税は、不動産売買契約書に貼付する収入印紙代として支払います。契約金額に応じて税額が決まり、購入時と同様の金額です。
電子契約を利用すれば印紙税は一切かからないため、コスト削減の観点から検討する価値があります。
登録免許税
売却時の登録免許税は、抵当権抹消登記を行う際に発生します。住宅ローンが残っている物件を売却する場合、決済と同時に抵当権を抹消する必要があるためです。
抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。土地と建物がある場合は2,000円、マンションの場合は敷地権付き区分建物として1,000円となります。
司法書士に依頼する場合は、登録免許税のほかに報酬として1万円から2万円程度の費用がかかります。
相続時に発生する税金


不動産投資をしている方が亡くなった場合、相続人には相続税が課税される可能性があります。相続税は相続財産の評価額から基礎控除額を差し引いた金額に対して課税され、税率は10%から55%の累進課税です。
基礎控除額は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」です。例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)となります。
不動産の相続税評価額は、土地については路線価または固定資産税評価額、建物については固定資産税評価額で計算します。一般的に時価の7割から8割程度となるため、現金で相続するよりも相続税を軽減できます。
また、賃貸用不動産の場合は貸家建付地や貸家の評価減により、さらに評価額を下げることが可能です。これらの特例を活用することで、相続税対策としての不動産投資の効果を高められます。


不動産投資にかかる所得税と住民税をシミュレーション


実際の不動産投資における税負担を理解するため、具体的な数値を使ってシミュレーションしてみましょう。年収600万円のサラリーマンが投資用ワンルームマンションを購入したケースで計算します。
- 年間家賃収入120万円
- 年間必要経費60万円(管理費、修繕積立金、固定資産税、減価償却費等)
この場合の不動産所得は60万円(120万円-60万円)となります。給与所得400万円と合算した総所得金額は460万円となり、所得税率は20%、住民税率は10%が適用されます。
不動産所得60万円に対する所得税は約12万円、住民税は約6万円となり、合計18万円の税負担が発生します。年間家賃収入120万円に対する実効税率は15%程度となる計算です。
不動産投資で税負担を軽減する方法
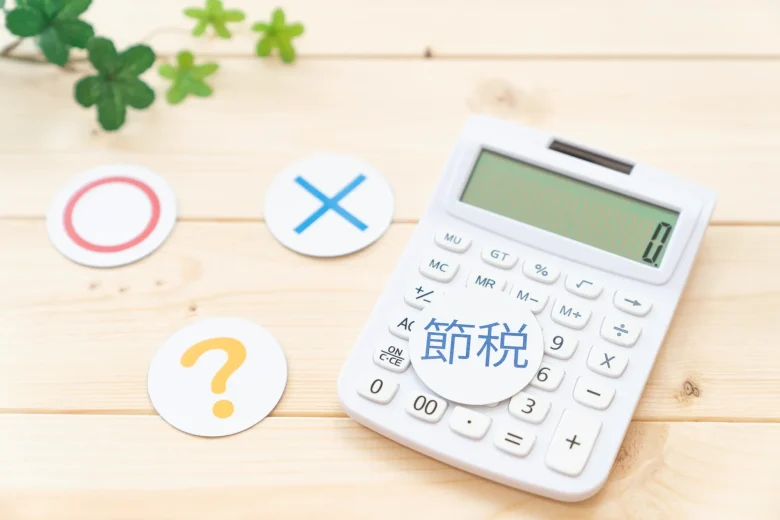
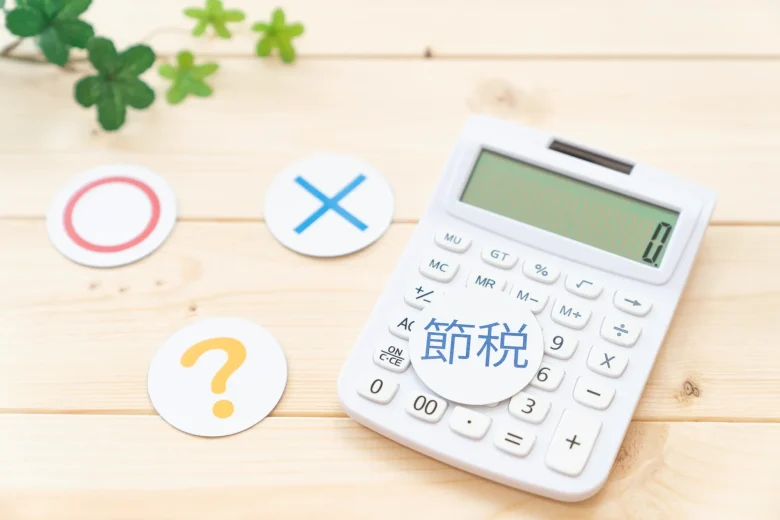
不動産投資の収益性を高めるためには、適切な節税対策が欠かせません。合法的な方法で税負担を軽減することで、手取り収入を増やし、投資効率を向上させることができます。
ここでは、初心者でも実践できる効果的な節税方法を4つ紹介します。
青色申告特別控除を活用する
青色申告特別控除は、不動産投資による所得から最大65万円を差し引ける制度です。白色申告と比べて帳簿付けの手間はかかりますが、大幅な節税効果が期待できます。
65万円の控除を受けるには、複式簿記による記帳と貸借対照表・損益計算書の作成が必要です。また、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行う必要があります。これらの条件を満たさない場合は55万円の控除となります。
青色申告を始めるには、不動産投資を開始した年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう。
不動産所得が100万円ある場合、青色申告特別控除65万円を利用すれば課税所得は35万円まで圧縮できます。税率20%の場合、約13万円の節税効果があります。
必要経費を漏らさず計上する
不動産投資では多くの費用が必要経費として認められるため、漏れなく計上することで大幅な節税が可能です。経費の計上漏れは税負担を重くする最大の要因となります。
なお、主な必要経費は以下のとおりです。
- 管理費
- 修繕費
- 広告宣伝費
- 損害保険料
- 借入金利息
- 税理士報酬
- 交通費
- 通信費
- 新聞図書費
- 不動産投資に関連する書籍代、セミナー参加費
特に見落としがちなのが、物件見学時の交通費や不動産投資の勉強代です。これらも事業に必要な支出として経費計上が可能です。
経費の適切な計上により、課税所得を大幅に圧縮し、所得税・住民税の負担を軽減できます。
減価償却費を漏らさずに計上する
減価償却費は、建物の購入代金を法定耐用年数にわたって経費として計上する方法です。実際の現金支出を伴わずに経費を計上できるため、効果的な節税手段となります。
木造建物の法定耐用年数は22年、鉄筋コンクリート造は47年です。中古物件の場合は、残存耐用年数または「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」で計算した年数のいずれか短い期間となります。
例えば、築10年の鉄筋コンクリート造マンション(建物価格1,500万円)を購入した場合で考えてみましょう。この物件の残存耐用年数は39年となり、年間の減価償却費は約38万円です。
減価償却費は毎年自動的に計上されるものではなく、確定申告で適切に処理する必要があります。計上漏れがないよう注意しましょう。
赤字が発生したら損益通算をする
不動産投資で赤字が発生した場合、給与所得や事業所得などのほかの所得と損益通算することで全体の税負担を軽減できます。
例えば、給与所得500万円で不動産所得マイナス100万円の場合、総所得金額は400万円となります。給与所得のみの場合と比べて、所得税・住民税合わせて約30万円の軽減効果があります。
特に投資初年度は、不動産取得税や登録免許税、仲介手数料などの初期費用により赤字になりやすい傾向があります。これらの費用も適切に経費計上することで、大幅な節税が可能です。
ただし、損益通算ができるのは不動産所得の赤字のみで、譲渡損失はほかの所得と通算できない点に注意が必要です。
まとめ
不動産投資には購入時・運用時・売却時・相続時のそれぞれで異なる税金が発生します。これらの税金を正しく理解し、適切な対策を講じることで投資収益を最大化できます。
特に重要なのは、青色申告特別控除の活用、必要経費の漏れない計上、減価償却費の適切な処理、損益通算の活用です。これらの節税方法を組み合わせることで、大幅な税負担軽減が期待できます。
不動産投資を成功させるためには、物件選びだけでなく税務知識も重要な要素となります。複雑な税務処理については税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
よくある質問




穴吹興産株式会社 不動産ソリューション事業部
アセットマネジメントグループ課長 穴吹 章彦
【資格】
・宅地建物取引士
・不動産証券化協会認定マスター
【経歴】
ソリューション事業部の業務に7年従事し、投資用不動産のアセットマネジメント業務を経験。現在は不動産特定共同事業におけるファンドの組成業務に従事し、投資家との契約業務全般を担当。不動産クラウドファンディングの仕組みや専門用語を解説しながら、情報発信を行っている。