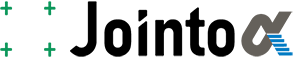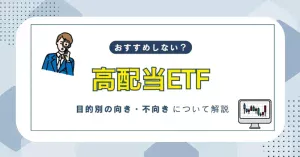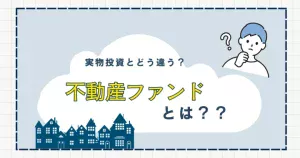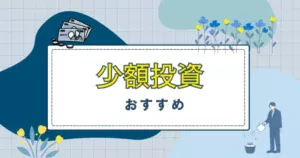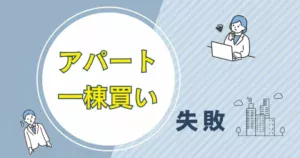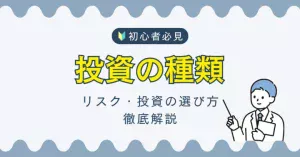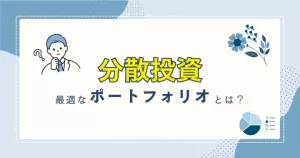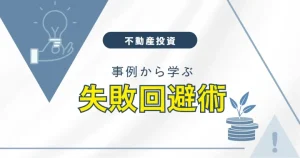IRRとは、投資の収益性を測るための指標です。投資をする際に役立つ情報であるため、計算方法を知っておくと役立ちます。
今回は、不動産投資の際にIRRを確認すべき理由や計算方法などを解説します。効率よく資産運用をするためにも、ぜひ参考にしてみてください。
・IRRとはなにか
・IRRと利回りの違い
・IRRを活用するメリットと活用法
IRRとは投資の収益性を示す指標

IRR(Internal Rate of Return:内部収益率)とは、投資の収益性を年率ベースで示す代表的な指標です。
簡単にいうと、「この投資は1年あたりでどれくらいお金を増やす力があるのか」を表すものです。
ある物件に1,000万円を投資して、将来得られる家賃収入や売却益をすべて含めた結果、年5%の効率で資金が回収できる場合、IRRは5%となります。
IRRの最大の特徴は、お金の「時間的価値」を考慮している点です。たとえ同じ100万円でも、今受け取る100万円と10年後に受け取る100万円では、その価値は異なります。IRRは、こうした時間の経過による価値の変化を計算に含めることで、実際の投資成果により近い数字といえます。
IRRと利回りの違い

不動産投資の収益性を測るうえで、最もよく使われるのが「利回り」という指標です。物件選びの際に「利回り◯%」という表記を見て判断する方も多いでしょう。
しかし、利回りはわかりやすい反面、見えない要素を含まないざっくりした目安でもあります。
その一方で、IRR(内部収益率)は収益のタイミングまで含めて正確に投資効率を測るための指標です。 利回りとIRRは、一見似ているようで実はまったく異なる性質と役割を持っています。
表面利回りは「収益の大きさだけを見る指標」
表面利回りとは、年間の家賃収入を物件価格で割って求めるシンプルな指標です。
年間の家賃収入 ÷ 物件価格 × 100
(例)
年間家賃収入120万円÷物件価格2,000万円×100=表面利回り6%
この数値は、物件の収益性をざっくり比較するのに役立ちますが、実際の運用では以下のようなコストが発生します
- 管理費・修繕積立金
- 固定資産税
- 空室リスク
- 仲介手数料や広告費
これらのコストは、表面利回りでは一切加味されていません。
そのため、あくまで「理想的な条件下での収益性」と捉えるべきです。
実質利回りは「コストを加味した現実的な指標」
実質利回りは、表面利回りに対し、諸経費を差し引いて再計算した数値です。
実際に手元に残る金額に近づくため、よりリアルな投資判断が可能になります。
ただし、実質利回りにも欠点があります。それは、「お金がいつ戻ってくるのか」という時間的な要素を含まないことです。
同じ年間収益でも、「毎月少しずつもらう」場合と「5年後に一括で受け取る」場合では、投資効率は大きく異なります。実質利回りではその差を表現できません。
IRRは「お金の回収タイミングまで見える指標」
IRR(内部収益率)は、将来得られるキャッシュフローの金額と受け取るタイミングを考慮して、お金がいつ・どれだけ入ってくるのかをすべて考慮して、「この投資は年率でどれくらいの効率でリターンを生むか」を数値化する指標です。
たとえば、次のような2つの投資案件があったとします。
表面利回りや実質利回りで見ればどちらも同じ「5%」ですが、資金を早く回収できるAの方が再投資のチャンスが多く、結果的に投資効率は高くなります。
IRRは、この違いを数値で見える化できるため、より本格的な投資判断が可能になります。
| 指標 | 主な特徴 | 用途 |
|---|---|---|
| 表面利回り | 賃料収入の総額を物件価格で割った単純な数値。 経費やリスクは未考慮。 | 物件の収益性をざっくり比較する初期判断材料。 |
| 実質利回り | 管理費・税金などを含めたより現実的な利回り。 回収タイミングは未考慮。 | 実際の手取り収益を見積もるための参考指標。 |
| IRR | キャッシュフローの金額とタイミングを考慮した投資効率の指標。 | 異なる投資案件を時間軸含めて正確に比較したいときに使用。 |
不動産投資の際にIRRを確認すべき理由
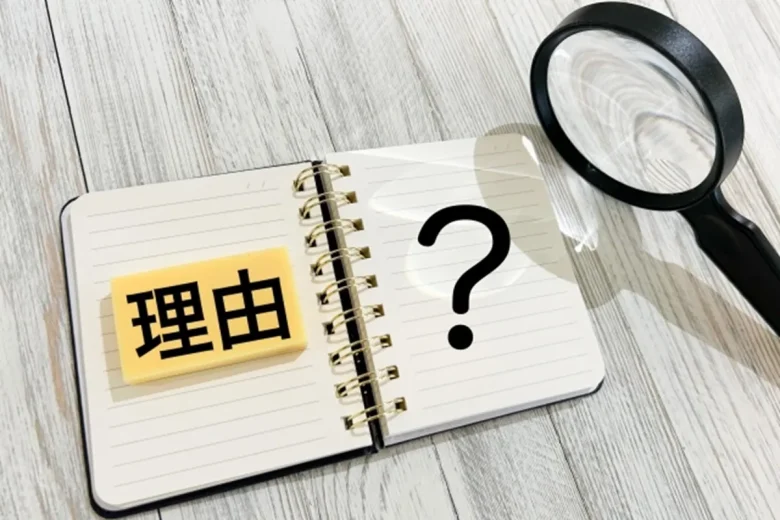
では、なぜ不動産投資においてIRRがこれほど重要なのでしょうか。その理由は主に4つあります。
投資期間を考慮して収益性を評価できるから
不動産投資は、数年から数十年という長期にわたるのが一般的です。このような長期投資においては、単年ベースの利回りだけで判断すると、短期的な収益性に引っ張られてしまい、実際の投資効率を見誤るリスクがあります。
IRRは、将来得られるキャッシュフローの金額だけでなく、その受け取るタイミングも加味して、年率ベースでの投資効率を算出します。
たとえば「5年で売却するプラン」と「20年間保有するプラン」のように、運用期間が異なる投資案件でも、IRRを使えばその違いを客観的に比較することができます。
投資回収期間の早さを判断できるから
IRRが高いということは、それだけ資金が早く回収できている、投資効率が良いということを意味します。
たとえば、同じ利回りでも、毎月分配される案件と満期一括型の案件では、IRRが大きく異なるケースがあります。
手元資金を次の投資に回したい場合や、キャッシュフローを重視する投資家にとって、IRRは投資のスピード感を測る重要な指標となります。
異なる投資案件の収益性を客観的に比較できるから
「新築ワンルームマンションを10年運用」と「中古アパートを5年運用して売却」のように、価格も運用期間もキャッシュフローの出方も全く異なる投資案件があったとします。こうした前提条件の異なる案件を利回りだけで比較することは難しいですが、IRRを使えばすべての案件を「年率リターン」という共通の尺度で比較できるようになります。
つまり、IRRは投資対象が異なる場合でも、公平かつ定量的にどちらが効率的かを見極められる指標なのです。
プロの不動産投資家も重視する指標だから
IRRは、個人投資家だけでなく、不動産ファンドや機関投資家など、プロの世界でも広く採用されている指標です。資金調達や投資採算性の評価、複数プロジェクトの並行検討など、IRRを使うことでより正確で戦略的な判断が可能になります。
不動産投資におけるIRRの計算方法
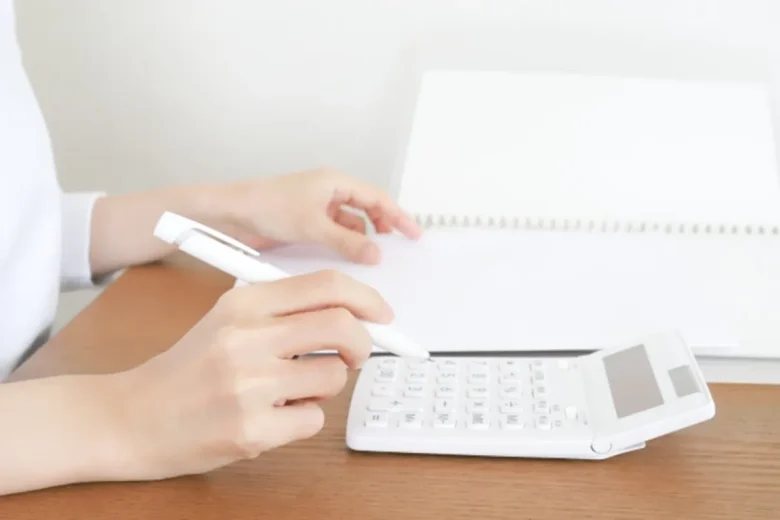
IRR(内部収益率)は投資効率を正確に評価できる指標ですが、その計算式は複雑で、手計算で求めるのは現実的ではありません。そのため、一般的にはExcelやGoogleスプレッドシートの関数を使って算出します。
ここでは、Excelの「XIRR関数」を使った計算例を、中古物件と新築物件の事例で見ていきましょう。
中古物件の事例
【投資条件】
- 購入価格
-
1,500万円(仲介手数料・登記費用など含む)
- 運用期間
-
5年間
- 年間収益(手取り)
-
90万円
- 実質利回り
-
6%
- 5年後の売却価格
-
1,400万円
- 売却時の諸経費
-
50万円
【キャッシュフロー例】
| 年数 | キャッシュフロー(円) | 内容 |
|---|---|---|
| 0年目 | -15,000,000 | 物件購入(初期投資) |
| 1年目 | +900,000 | 年間収益(1年目) |
| 2年目 | +900,000 | 年間収益(2年目) |
| 3年目 | +900,000 | 年間収益(3年目) |
| 4年目 | +900,000 | 年間収益(4年目) |
| 5年目 | +14,400,000 | 年間収益(5年目)+売却益(1,400万円 − 50万円) |
このように、各年の収入をExcelの表に入力し、対応する日付を設定したうえで「XIRR関数」で計算すれば、おおよそ年4.5%程度のIRRが得られる想定です。
この数値は、物件購入価格と毎年の収入・最終売却益をすべて考慮した実質的な投資効率を示しています。
新築物件の事例
【投資条件】
- 購入価格
-
2,800万円(新築マンション)
- 運用期間
-
10年間
- 年間収益(手取り)
-
120万円(初年度以降1%ずつ減少)
- 実質利回り
-
4.2%(※1年目)
- 5年後の売却価格
-
2,600万円
- 売却時の諸経費
-
70万円
【キャッシュフロー例】
| 年数 | キャッシュフロー(円) | 内容 |
|---|---|---|
| 0年目 | -28,000,000 | 物件購入(初期投資) |
| 1年目 | +1,200,000 | 年間収益(1年目) |
| 2年目 | +1,188,000 | 年間収益(2年目:1%減) |
| 3年目 | +1,176,000 | 年間収益(3年目:1%減) |
| ~ | ~ | ~ |
| 10年目 | +26,392,000 | 年間収益(10年目)+売却益(2,600万円 − 70万円) |
このように10年間の家賃減少と最終的な売却価格を反映して「XIRR関数」で計算すると、IRRは約3.4%前後となる想定です。
一見、実質利回りが高そうに見える物件でも、長期保有による家賃下落や売却損失・諸経費を含めて見ると、IRRは大きく下がることがあるという点に注意が必要です。
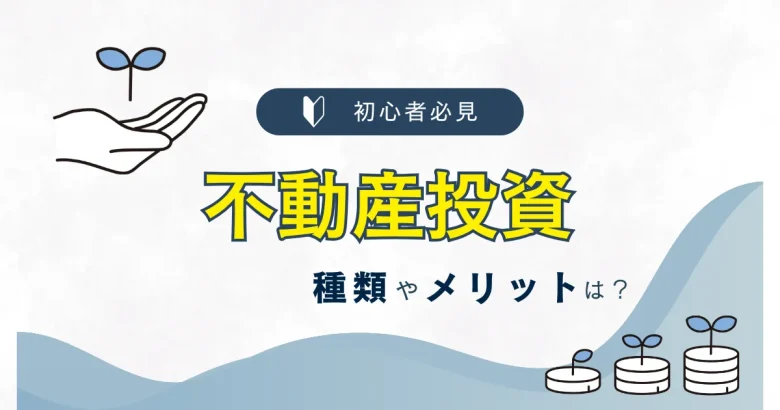
IRRが高い物件の特徴

IRR(内部収益率)は、物件から得られる収益だけでなく、資金の回収タイミングや保有期間を含めた投資効率を数値化する指標です。
では、どのような不動産がIRRの高い案件になりやすいのでしょうか。
ここでは、一般的にIRRが高くなる傾向にある物件の3つの特徴をご紹介します。
立地・エリアがよい
最も基本かつ重要な要素が、立地の良さです。
駅からの距離が近い、商業施設や公共機関が整っているなど、利便性の高いエリアにある物件は、安定した賃貸需要が見込め、空室リスクが低くなります。
さらに、好立地の物件は資産価値が下がりにくく、将来的に高い価格での売却が期待できる点も魅力です。このように、家賃収入と売却益の両面からIRRを押し上げる要素が揃っているため、立地条件は投資判断において確認すべきポイントとなります。
取得価格が相対的に安い
同じエリア・同じ規模の物件でも、取得価格が相対的に安ければ、IRR(投資効率)は高くなる傾向があります。なぜなら、同じ収益を得られるなら、初期投資額が少ないほうがリターンは高くなるからです。
ただし、価格が安いからといってすぐに飛びつくのは危険です。
老朽化の進行、立地条件、法的制約(再建築不可や接道義務など)など、価格が安い理由を冷静に見極める必要があります。
そのうえで、市場価格や周辺の取引事例を調査し、割安かつ将来性のある物件を選ぶことが、IRR向上に直結します。
賃貸需要が大きい
IRRにおいては、家賃収入の安定性と継続性が非常に重要です。
そのため、エリア内に十分な賃貸需要があるかどうかは、投資判断において見逃せないポイントとなります。
例えば、以下のような物件は高い賃貸需要が見込まれやすく、IRRも高くなりやすい傾向があります。
- 単身者向け:駅近・都心・大学やオフィス街周辺
- ファミリー向け:保育園や学校、公園、スーパーが揃った住宅エリア
- 高齢者向け:医療機関が近く、バリアフリー対応済み
こうした物件は、空室リスクが低く、長期的に安定した稼働が見込めるため、キャッシュフローが安定し、結果としてIRRも高水準を維持しやすくなります。
逆に、利回りが高くても空室リスクの高いエリアでは、実際の収益が不安定となり、IRRが低下してしまうケースも少なくありません。
そのため、利回りの高さだけでなく、需要の強さにも注目することが重要です。
知っておくべきIRRの問題点

IRRは不動産投資の収益性を評価する上で非常に優れた指標ですが、万能ではありません。利用する際にはいくつかの注意点を理解しておく必要があります。
投資規模を考慮できない
IRRはあくまで「投資効率」を表す指標であり、投資によって得られる絶対的な利益の大きさを評価するものではありません。
例えば以下のような2つの案件を比べたとします
IRRの数値だけを見ると案件Aの方が優れているように見えます。しかし、得られる利益の絶対額は案件Bの方が圧倒的に大きくなります。
複数の案件を比較する際は、IRRと合わせて利益の絶対額も確認することが大切です。
リスクの反映が完全ではない
IRRを計算する際に使う将来のキャッシュフロー(家賃収入や売却価格)は、あくまで「予測値」です。
例えば、以下のようなリスクは、IRRの数値に直接反映されません。
- 空室が想定より長引く
- 修繕費用や税金が想定以上にかかる
- 売却時に予定価格で売れない
つまり、IRRは「前提条件がすべて想定通りに進んだ場合の理想的な数値」であり、実際の投資リスクや不確実性は別途考慮する必要があります。
さまざまな不確実性を織り込む必要がある
IRRは数値的に説得力がある一方で、将来起こりうる不確実な事象すべてを反映できるわけではありません。金利の上昇によるローン返済額の増加や、法改正、自然災害など、不動産投資には予測が難しい不確実な要素が常に存在します。
IRRのシミュレーションは複数のパターン(楽観的なケース、悲観的なケースなど)を用意し、あくまで投資判断の一つの材料として活用することが重要です。
まとめ
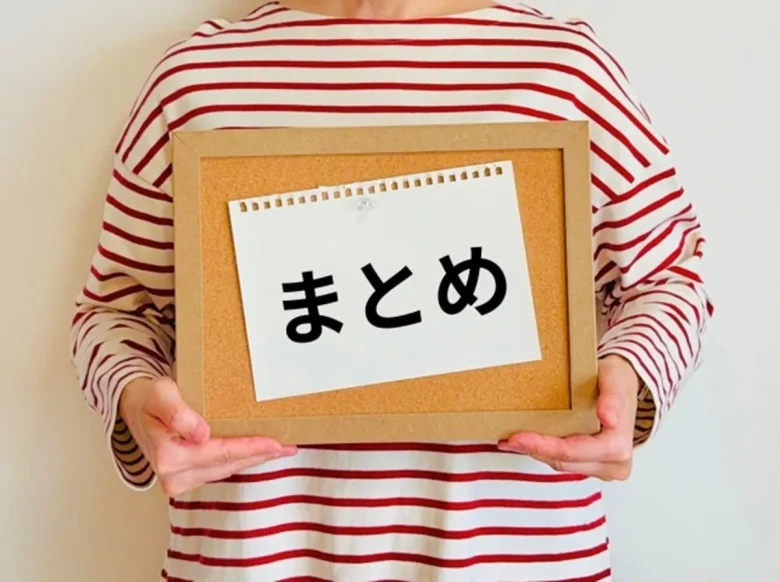
不動産投資における収益性を判断する際、つい「利回り」というわかりやすい数字に注目しがちです。
しかし、表面利回りや実質利回りだけでは、投資期間や資金の回収タイミング、最終的なリターンの効率性までは把握できません。
そこで重要になるのが、IRR(内部収益率)という投資効率を年率で測る指標です。
IRRを活用すれば、同じ利回りの案件であっても、より早く資金が回収できるものを選んだり、長期保有か短期売却かといった方針の違いを数値で比較したりと、より戦略的な判断が可能になります。
もちろん、IRRにも「投資規模を反映できない」「リスクを織り込みきれない」などの注意点はあります。
だからこそ、IRRを「唯一の基準」ではなく「投資判断を多角的に見るためのツールのひとつ」として活用する姿勢が大切です。表面的な利回りにとどまらず、資金の動きと時間の価値をふまえて判断することが、堅実な資産形成への第一歩です。
よくある質問


穴吹興産株式会社 不動産ソリューション事業部
アセットマネジメントグループ課長 穴吹 章彦
【資格】
・宅地建物取引士
・不動産証券化協会認定マスター
【経歴】
ソリューション事業部の業務に7年従事し、投資用不動産のアセットマネジメント業務を経験。現在は不動産特定共同事業におけるファンドの組成業務に従事し、投資家との契約業務全般を担当。不動産クラウドファンディングの仕組みや専門用語を解説しながら、情報発信を行っている。