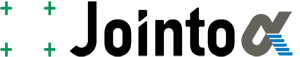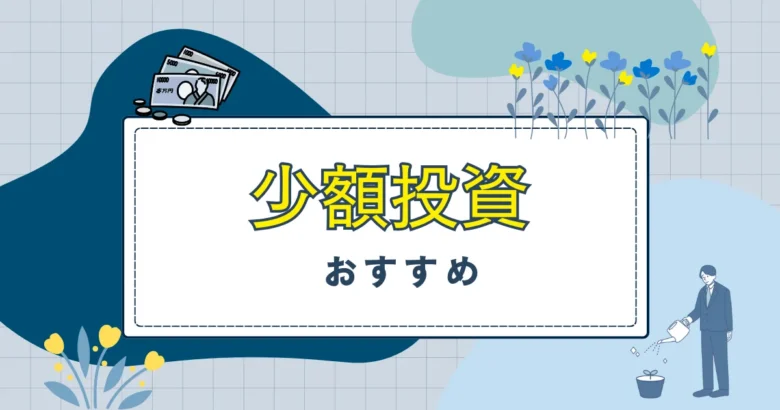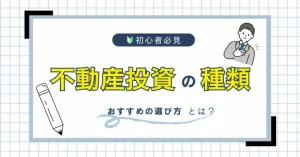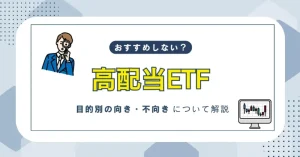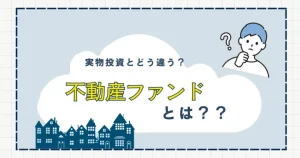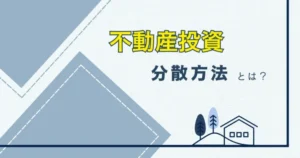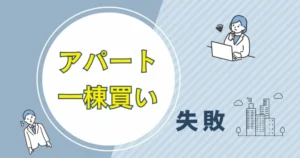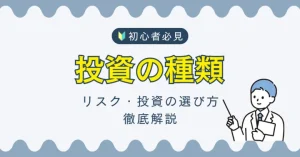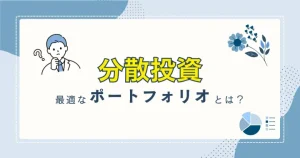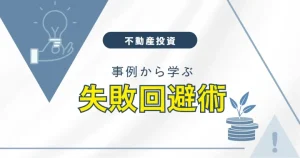「投資を始めたいけど、まとまった資金がない」「失敗が怖くて一歩踏み出せない」そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。リスクを抑えながら投資を始めたい方は、少額投資がおすすめです。
本記事では、少額投資の具体的な方法やメリットなどを比較します。
少額投資のメリット・デメリット
自分に合った投資方法の選び方
少額投資で失敗しないための方法
7つのおすすめ少額投資方法

少額投資には、リスクの低いものから高いものまで、さまざまな選択肢があります。
それぞれの投資方法には、最低投資額・リスク・リターン・運用の手間などに違いがあるため、自分の資金状況や投資目的に合わせて選ぶことが大切です。
定期預金は元本保証で安心
定期預金は元本が保証されているため、投資初心者にとって安心できる選択肢です。預金保険制度により、金融機関が破綻しても1,000万円とその利息までは保護されます。
ただし、現在の金利水準は非常に低く、メガバンクの普通預金金利は0.2~0.5%程度です。100万円を1年間預けても、利息はわずか200円程度にしかなりません。
インフレ(物価上昇)が進む環境では、実質的な資産価値が目減りする可能性もあります。そのため、定期預金は緊急時の備えとして活用し、余裕資金はほかの投資方法と組み合わせることをおすすめします。
投資信託は100円から購入可能
投資信託は、多くの投資家から集めた資金をプロが運用する金融商品です。証券会社によっては、100円という少額から購入できます。
投資信託のメリットは、少額で分散投資ができる点です。例えば、日本株式や米国株式、債券など、さまざまな資産に投資する商品を選べば、リスクを抑えながら運用できます。

初心者の方には、コストが低く、長期的に安定したリターンが期待できるインデックスファンドがおすすめです。
毎月一定額を自動で購入する積立設定にすれば、時間分散効果(ドルコスト平均法)も得られます。
ETFは手数料が安く分散投資しやすい
ETF(上場投資信託)は、証券取引所に上場している投資信託です。株式と同じように、市場が開いている時間帯にリアルタイムで売買できます。
ETFのメリットは、信託報酬が投資信託よりもさらに低い点です。代表的な商品では年0.05%程度のものもあり、長期投資においてコストを抑えられます。
最低投資額はETFの価格によって異なり、日本株のETFであれば数千円から数万円程度で購入できる銘柄も多くあります。
単元未満株の個別投資
単元未満株(ミニ株)のサービスを使えば、企業の株式を1株から購入できます。少額から個別株投資を始められ、株主優待や配当金も株数に応じて受け取れます。
デメリットは、売買できる時間が限られていることです。多くの証券会社では、前場(午前)・後場(午後)の始値など、決まった時間にしか取引できません。リアルタイムでの売買ができないため、思わぬ価格で約定する可能性もあります。
個別株投資は、企業分析や財務諸表の読み方など、ある程度の知識が必要です。まずは投資信託やETFで市場全体の動きに慣れてから、個別株投資に挑戦するのがよいでしょう。
REITで不動産投資を少額から実現
REIT(リート)は、不動産投資信託のことです。投資家から集めた資金で、オフィスビル・商業施設・マンションなどの不動産を購入し、賃料収入や売却益を投資家に分配します。



REITの魅力は、少額から不動産投資ができる点です。
実物不動産を購入するには数千万円から数億円の資金が必要ですが、REITなら数万円から投資できます。
REITは証券取引所に上場しているため、株式と同じように売買できます。換金性が高く、必要なときに現金化しやすい点もメリットです。
ただし、REITには価格変動リスクがあります。不動産市場の動向や金利の変動によって、価格が大きく下落する可能性もあります。


ロボアドバイザーは全自動で運用
ロボアドバイザーは、AI(人工知能)を活用して、自動で資産運用を行うサービスです。投資家のリスク許容度に応じて最適なポートフォリオを提案し、定期的にリバランス(資産配分の調整)も行ってくれます。
ロボアドバイザーのメリットは、投資の知識がなくても始められる点です。簡単な質問に答えるだけで、自分に合った運用プランが提案されます。また、自動積立設定にしておけば、定期的に投資を続けることも可能です。
デメリットは、手数料が比較的高いことです。運用資産に対して年1%程度の手数料がかかります。自分でインデックスファンドを購入する場合と比べると、コストは高くなります。
不動産クラウドファンディングはミドルリスクで運用
不動産クラウドファンディングは、インターネットを通じて複数の投資家から資金を集め、不動産プロジェクトに投資する仕組みです。1万円という少額から始められるサービスが多く、近年注目を集めています。
不動産クラウドファンディングの多くのサービスでは、「優先劣後方式」という仕組みを採用しています。
デメリットは、途中解約ができないことです。運用期間中は原則として換金できないため、すぐに必要になる可能性のある資金を投資するのは避けましょう。
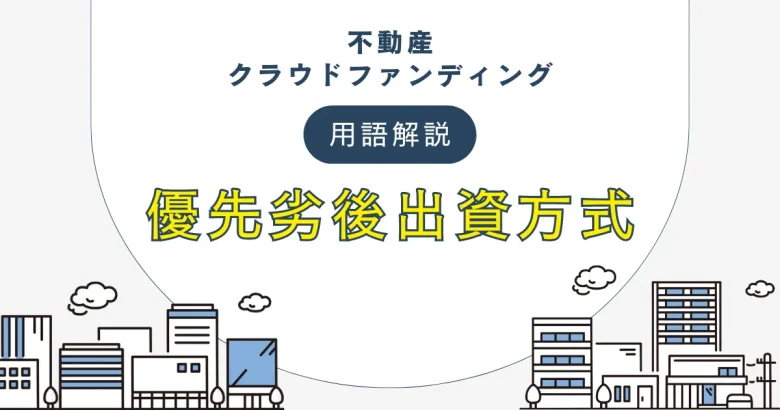
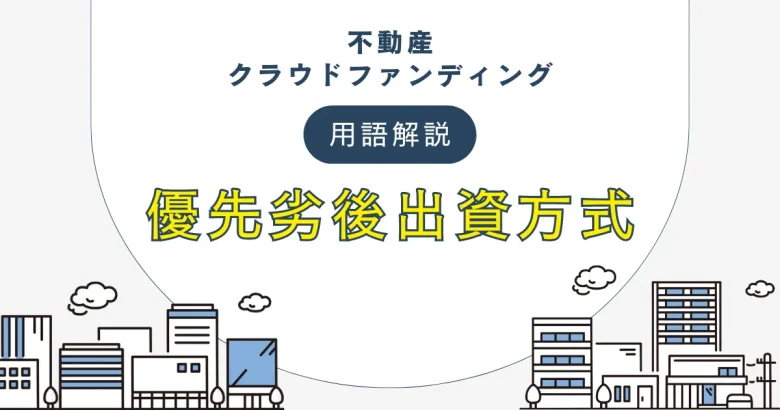
少額投資のメリット


少額投資には、初心者にとって大きな3つのメリットがあります。まとまった資金がなくても始められる上、リスクを抑えながら投資経験を積める点が特徴です。
投資額が少ないため損失も限定できる
少額投資のメリットは、万が一失敗しても損失が限定的である点です。



例えば、1万円を投資して価値が半分になっても、損失は5,000円で済みます。
投資には必ずリスクが伴います。しかし、少額から始めることで大きな損失を避けながら、実際の市場の動きや投資の仕組みを学べます。
また、少額で始めることで、感情のコントロールも学べます。投資では、価格が下落したときに慌てて売却してしまう「狼狽売り」が失敗の原因になりがちです。少額であれば、冷静に状況を判断する余裕が生まれます。
投資に慣れてきたら、徐々に投資額を増やすことをおすすめします。最初から大きな金額を投資するのではなく、段階的に資産を増やしていきましょう。
複数商品に分散投資できる
少額投資では、限られた資金でも複数の商品に分散投資できます。分散投資とは、投資先を複数に分けることで、特定の商品が値下がりしても、全体の損失を抑えられる手法です。
具体的には、国内株式・海外株式・債券・不動産など、異なる資産クラスに分散するのが効果的です。少額投資なら、これらの資産に数万円ずつ投資することも可能になります。
実践しながら投資を学べる
投資を通じて実際にお金を投じることで、投資を体験的に学べます。本や動画で知識を得ることも大切ですが、実際に投資してみなければ分からないことも少なくありません。
投資を始めると、市場のニュースや経済指標に自然と関心が向くようになります。自分のお金が投資されていることで、学習意欲も高まるでしょう。



例えば、日経平均株価が上昇したとき、自分が保有している投資信託やETFの価格がどう変動するのか、実際に確認できます。
為替レートの変動が、海外資産にどのような影響を与えるのかも体感できます。
少額投資のデメリット


少額投資には多くのメリットがある一方で、知っておくべきデメリットも存在します。これらのデメリットを理解した上で投資を始めることが、失敗を避けるために重要です。
ここでは、少額投資の3つの主なデメリットを解説します。事前にデメリットを把握しておけば、適切な対策を講じることができるでしょう。
大きな利益は期待できない
少額投資では、投資額が少ないため、得られる利益も限定的になります。



例えば、1万円を年利5%で運用しても、1年間で得られる利益はわずか500円です。
投資のリターンは、基本的に投資元本に比例します。10万円を運用すれば5,000円、100万円なら5万円のリターンになります。少額では、どれだけ高い利回りを実現しても、金額としては大きくなりません。
ただし、少額投資は「すぐに大きな利益を得る」ことではなく、「投資の経験を積む」「長期的な資産形成の基礎をつくる」ことが目的です。
最初は少額から始め、投資に慣れてきたら徐々に投資額を増やしていくとよいでしょう。
手数料の割合が高くなりやすい
少額投資では、投資額に対する手数料の割合が高くなりやすい点に注意が必要です。手数料が投資成果を圧迫し、思ったほどリターンが得られない可能性があります。



例えば、株式の売買手数料が1回100円の場合、1万円の取引では手数料率は1%になります。
一方、100万円の取引なら手数料率は0.01%です。投資額が小さいほど、手数料の負担が重くなります。
少額投資では、手数料が運用成績に与える影響が大きいため、コストを意識した商品選びを意識しましょう。
選べる商品や銘柄が限られる
少額投資では、購入できる商品や銘柄が限られることがあります。特に、個別株投資では、単元株制度(100株単位での取引)があるため、高額な銘柄は購入できません。
例えば、1株1万円の銘柄を購入するには、単元株で100万円が必要です。投資資金が10万円の場合、この銘柄には投資できません。
単元未満株のサービスを利用すれば、1株から購入できますが、前述のとおり、売買時間が制限されるなどのデメリットがあります。また、すべての銘柄が単元未満株取引に対応しているわけではありません。
自分に合った投資方法の選び方


少額投資にはさまざまな選択肢がありますが、すべての人に最適な投資方法があるわけではありません。自分の状況や目的に合わせて、適切な投資方法を選ぶことが重要です。
ここでは、投資方法を選ぶ際の4つの重要なポイントを解説します。
最低投資額と手数料を比較する
投資方法を選ぶ際は、まず最低投資額と手数料を確認しましょう。自分が用意できる資金と、コストのバランスを考えることが大切です。
最低投資額は、投資方法によって異なります。投資信託は100円から、ETFは数千円から、単元株は数万円から数十万円、不動産クラウドファンディングは1万円からというのが一般的です。
以下は、主な投資方法の最低投資額と手数料の目安を比較した表です。
| 投資方法 | 最低投資額 | 主な手数料 |
|---|---|---|
| 投資信託 | 100円~ | 信託報酬(年0.1~2%) |
| ETF | 数千円~ | 売買手数料+信託報酬(年0.05~0.5%) |
| 単元未満株 | 数百円~ | 売買手数料(0~数百円) |
| REIT | 数万円~ | 売買手数料 |
| ロボアドバイザー | 1万円~ | 運用手数料(年1%程度) |
| 不動産クラウドファンディング | 1万円~ | なし |
手数料には、購入時手数料・信託報酬・売買手数料・為替手数料などがあります。これらの手数料は、長期的には運用成績に大きな影響を与えるため、軽視すべきではありません。
リスクとリターンのバランスを確認する
投資では、リスクとリターンは表裏一体の関係にあります。高いリターンを期待できる投資ほど、大きなリスクも伴うため、自分のリスク許容度に合った投資方法を選びましょう。
リスク許容度とは、どの程度の損失まで受け入れられるかという指標です。年齢・収入・資産状況・投資経験・性格などによって、リスク許容度は異なります。
一般的に、若い世代ほどリスク許容度が高いとされています。これは、運用期間が長く、損失が出ても回復する時間があるためです。一方、定年退職が近い世代は、元本の安全性を重視すべきでしょう。
換金性の高さで選ぶ
換金性(流動性)とは、資産をどれだけ早く現金化できるかを示す指標です。急な支出に備えるためにも重要な要素です。
株式・ETF・REITなど上場商品は換金性が高く、市場時間内なら売却でき、通常2営業日後に現金化できます。
一方、定期預金は満期前解約で金利が大幅に下がるため実質的に換金性が低めです。
自分のライフプランに合わせて、換金性と収益性のバランスを考えた資産配分を行いましょう。
運用の手間と時間を考慮する
投資方法によって必要な手間は異なり、忙しい人には手間の少ない投資が向いています。ロボアドバイザーや積立型投資信託は、一度設定すれば自動的に購入・運用・リバランスが行われ、日々の値動きをチェックする必要もありません。
不動産クラウドファンディングも、投資後は運用状況の報告を確認するだけで、物件管理の負担は不要です。
一方、個別株投資やETFの売買は、企業の業績や市場動向を分析し、売買のタイミングを判断する必要があります。
投資の知識を深めたい方には適していますが、忙しい方には負担になるかもしれません。
少額投資で失敗しないための5つの方法


少額投資は初心者にとって始めやすい一方で、正しい知識や戦略がなければ、期待した成果が得られないこともあります。ここでは、少額投資で失敗しないための5つの重要なポイントを解説します。
投資の目標金額を明確にする
投資を始める前に、具体的な目標金額と達成時期を設定しましょう。目標が明確であれば、適切な投資方法や投資額を判断しやすくなります。
例えば…
「10年後に教育資金として300万円をためる」「20年後の老後資金として1,000万円を準備する」
といった具体的な目標です。目標金額と期間が決まれば、毎月いくら投資すればいいかが計算できます。
金融庁の「つみたてシミュレーター」を使えば、目標金額を達成するために必要な毎月の積立額や積立期間を簡単に計算できます。自身の目標金額と運用期間に応じて、投資計画を考えてみてください。
自分のリスク許容度を把握する
投資で失敗しないためには、自分のリスク許容度を把握することが重要です。許容度を超える投資は、価格変動に耐えられず損失時に焦って売却する原因になります。
許容度は年齢・収入・資産・家族構成・性格で異なります。
運用期間を長く取れるため、株式などリスクの高い商品の割合を増やせます。損失が出ても、長期的に回復する時間があるためです。
教育費や住宅ローンなどの支出がある一方、収入も安定しています。リスクとリターンのバランスを取った投資が適しています。
元本の安全性を重視すべきです。大きな損失が出ると、回復する時間が限られているためです。
また、性格もリスク許容度に影響します。価格が10%下落したときに、「安く買えるチャンス」と考えられる方は、リスク許容度が高いといえます。一方、夜も眠れないほど心配になる方は、リスク許容度が低いでしょう。
積立投資を継続する
少額投資で成功するための重要な方法は、積立投資を長期間継続することです。毎月一定額を投資することで、時間分散効果とドルコスト平均法の恩恵を受けられます。



ドルコスト平均法とは、価格が高いときは少なく、安いときは多く購入して平均購入単価を平準化する手法です。
例えば、毎月1万円で投資信託を購入する場合
価格が1万円のときは1口、5千円のときは2口購入できます。
複利効果により、資産を成長させられる点もメリットの一つです。運用効率を高めるためにも、10年・20年と長期的な視点で継続しましょう。
いきなり全額を投資しない
投資を始める際は、手元資金を一気に投じるのは避け、まず少額から始めることが重要です。



例えば50万円の投資可能資金があれば、最初は10万円ほどにし、
残りは預金として保管しながら徐々に増やすのが安全です。
一度に全額投資すると、直後の下落で大きな含み損が発生し、精神的負担で冷静な判断が難しくなります。
ただし、長期的な積立投資を行う場合は、この限りではありません。積立投資は時間分散が前提のため、早く始めるほど複利効果が大きくなります。
手元資金を一度に投資するのではなく、毎月の給料から積立する形であれば、タイミングを気にする必要はありません。
短期の値動きに一喜一憂しない
少額投資の失敗原因として、短期的な値動きに反応して感情的に売買してしまうことが挙げられます。株価は日々上下し、短期の変動を正確に予測することは困難です。
短期的な値動きに一喜一憂すると、高値で買って安値で売ってしまったり、頻繁な売買で手数料がかさんでしまったりする可能性があります。短期売買を繰り返すと、その都度手数料がかかり、利益が減ってしまいます。
市場が一時的に下落しても、それは長期投資における「通過点」に過ぎません。冷静さを保ち、投資計画を守ることが、少額投資を成功させるポイントです。
不動産クラウドファンディングが注目される理由


不動産クラウドファンディングは、少額投資の選択肢の中でも注目を集めている投資方法です。従来は富裕層や機関投資家しかアクセスできなかった不動産投資を、一般の個人投資家でも手軽に始められるようになりました。
ここでは、不動産クラウドファンディングが注目される5つの理由を詳しく解説します。
数万円から不動産投資ができる
不動産クラウドファンディングの最大の魅力は、1万円という少額から不動産投資ができる点です。
実物不動産を購入する場合、数千万円から数億円の資金が必要になりますが、クラウドファンディングなら誰でも気軽に始められます。
例えば、10万円の資金があれば、10件のプロジェクトに投資して、リスクを分散できます。
投資対象となる不動産も多岐にわたります。都心のオフィスビル・商業施設・マンション・ホテル・物流施設など、個人では購入が難しい大型物件にも少額から投資することが可能です。
運用の手間が一切かからない
不動産クラウドファンディングでは、物件の管理や運用はすべて事業者が行います。投資家は出資するだけで、後は配当を受け取るのを待つだけです。
投資後は、定期的に送られてくる運用報告を確認するだけで済みます。
仕事や家事で忙しい方、不動産投資の経験がない方でも、安心して始められるのが大きなメリットです。



また、居住地に関係なく全国の物件に投資できるため、地方在住の方でも都心の優良物件に投資できます。
優先劣後方式で投資家が保護される
不動産クラウドファンディングの多くは、「優先劣後方式」という仕組みを採用しています。この仕組みにより、投資家のリスクが軽減され、元本の安全性が高まります。
優先劣後方式とは、投資家を「優先出資者」、事業者を「劣後出資者」として、損失が発生した場合、まず事業者が損失を負担する仕組みです。
1億円の不動産プロジェクトで、投資家が8,000万円(優先出資80%)、事業者が2,000万円(劣後出資20%)を出資したとします。
運用終了時に不動産の価値が9,000万円に下落した場合、1,000万円の損失が発生します。しかし、この損失はまず事業者の出資分2,000万円から差し引かれます。投資家の元本8,000万円は守られるのです。
不動産の価値が7,500万円まで下落した場合でも、2,500万円の損失のうち、2,000万円は事業者が負担します。投資家の損失は500万円にとどまります。
この仕組みは、投資初心者にとって安心材料となります。元本保証ではありませんが、一定のリスク軽減策が講じられている点は、ほかの投資方法にはない特徴です。
想定利回りが事前に分かる
不動産クラウドファンディングでは、投資する前に想定利回りと運用期間が明示されています。投資判断をする際の重要な情報が、事前に把握できるのです。
想定利回りはプロジェクトによって異なるものの、年3%から7%程度が一般的です。



例えば、想定利回り年6%、運用期間12カ月のプロジェクトに10万円を投資した場合、運用終了時には約6,000円の分配金(税引前)が期待できます。
ただし、想定利回りはあくまで「想定」であり、保証されたものではありません。空室率の上昇や賃料の下落などにより、実際の利回りが想定を下回る可能性もあります。
ほかの投資と組み合わせやすい
不動産クラウドファンディングは少額で始められるため、ほかの投資と組み合わせやすい点が魅力です。
株式・債券・不動産など異なる資産を組み合わせる「分散投資」を行うことで、全体のリスクを抑えつつ安定したリターンを狙えます。
複数の投資方法を組み合わせれば、各投資のメリットを生かしながらデメリットを補完できます。自分の目的とリスク許容度に合ったポートフォリオを作りましょう。
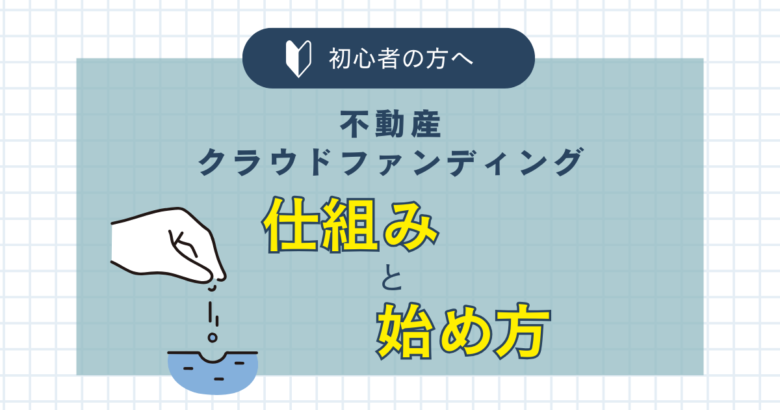
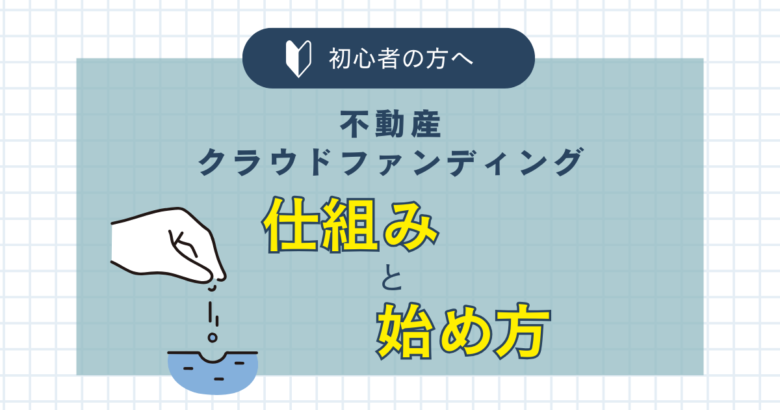
まとめ


少額投資は、方法次第では100円から始められる投資方法として、初心者でも気軽に資産形成をスタートできる選択肢です。
投資方法を選ぶ際は、最低投資額と手数料を比較し、リスクとリターンのバランスを確認することが大切です。
また、換金性の高さや運用の手間も考慮して、自分のライフスタイルに合った方法を選びましょう。
少額投資に関するよくある質問


- 少額投資でも、分散投資は本当に効果がありますか?どれくらい分散すればいいのでしょうか?
-
はい、少額投資でも分散投資は十分効果があります。
ポイントは「資産の種類を分けること」で、金額の大小はあまり関係ありません。
例えば、国内株式、海外株式、債券、不動産(REIT・クラウドファンディング)など、値動きの異なる3〜4種類の資産に分散させるとバランスが良くなります。 - 少額投資を続けるうえで、どれくらいの頻度で運用状況をチェックすべきですか?
-
少額投資は長期運用が前提のため、毎日の値動きを気にする必要はありません。
初心者におすすめのチェック頻度は、月1回、もしくは 四半期に1回(3ヶ月に1回)で十分です。 - 少額投資はNISAを使った方が有利ですか?
-
少額投資こそ、NISAを使った方が圧倒的に有利です。
NISAのメリットとして「運用益・売却益・配当が非課税、長期で積立しても税金がかからない、手数料の低い商品も多い」という点があります。通常口座では、利益に対して約20%の税金(譲渡益税)がかかりますが、NISAならこれが0円になります。
- 少額投資を始めた後、相場が大きく下落したらどうすればいいですか?
-
基本的には、慌てて売らず、そのまま続けるのが正解です。下落局面は、積立なら「安く多く買えるチャンス」、長期投資なら「通過点」という側面があります。
- 生活防衛資金はどれくらい確保しておけば、安心して少額投資を始められますか?
-
一般的には、3〜6ヶ月分の生活費を生活防衛資金として確保するのが目安です。
例:生活費が月20万円 → 60〜120万円を確保この資金は、急な出費・病気・リストラなどの際に備えるためのものなので、投資には回さない方が安全です。


穴吹興産株式会社 不動産ソリューション事業部
アセットマネジメントグループ課長 穴吹 章彦
【資格】
・宅地建物取引士
・不動産証券化協会認定マスター
【経歴】
ソリューション事業部の業務に7年従事し、投資用不動産のアセットマネジメント業務を経験。現在は不動産特定共同事業におけるファンドの組成業務に従事し、投資家との契約業務全般を担当。不動産クラウドファンディングの仕組みや専門用語を解説しながら、情報発信を行っている。