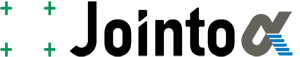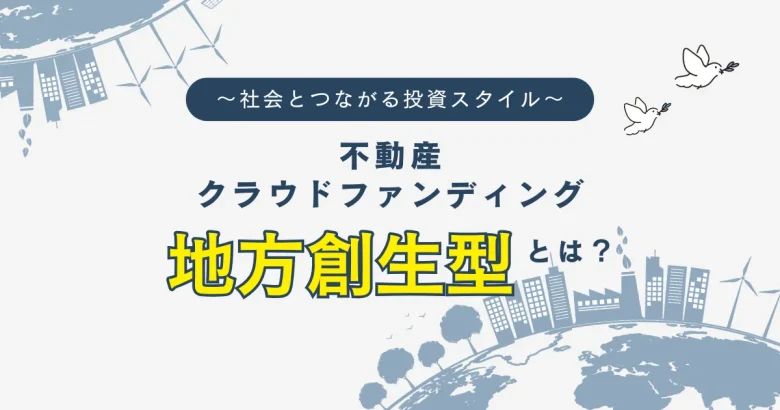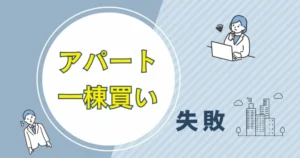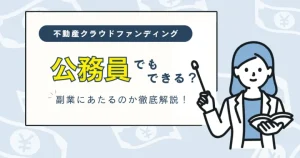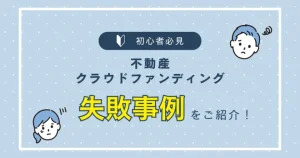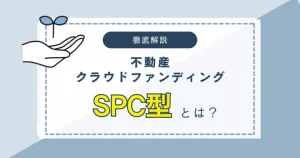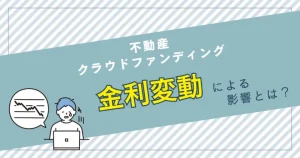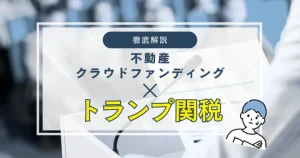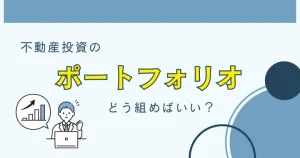「せっかく投資をするなら、誰かの役に立つことにもつながったら嬉しいのに」という想いを抱く人が今少しずつ増えています。老後資金の準備やインフレ対策として、資産形成の重要性が高まる中で、不動産クラウドファンディングを通じて社会や地域とのつながりを意識する投資手法にも注目が集まっています。
あなたの投資が、地域の課題を解決し、まちの未来を支える力になる。そんな「地方創生型投資」が、今では少額から誰でも始められる時代になっています。
本記事では、なぜ今、地方が投資先として注目されているのか、そして不動産クラウドファンディングを通じてどのように地域を支えられるのかについて、分かりやすく解説します。
今、地方が投資先として注目されている理由
不動産クラウドファンディングで地域に貢献できる仕組み
自分にあった地方創生型投資の始め方と選び方
不動産クラウドファンディングとは?

まずは、「不動産クラウドファンディング」とは何か、簡単に説明します。仕組みをすでにご存知の方も、改めて不動産クラウドファンディングの魅力を確認してみてください。
忙しい人でもできる、手間いらずの不動産投資
不動産クラウドファンディングは、スマホひとつで簡単に始められる、手軽な不動産投資の一種です。従来の不動産投資(現物不動産)のように、物件を購入したり入居者対応や管理業務を行ったりといった手間は一切なく、物件選定から管理・運用まですべてを運営会社が行ってくれます。そのため、忙しい会社員の方でも、手間や時間をかけずに不動産投資に参加することができます。運用期間終了まで管理や複雑な手続きも必要ありません。
1口1万円からと少額から始められることも魅力のひとつで、投資初心者の方にも人気が高まっています。

「資産形成はしたいけど、不動産投資はハードルが高い」と感じていた方にこそ、ぴったりな選択肢です。
なぜ今「地方創生」が注目されているのか


資産運用の選択肢として「地方創生に関わる投資」が注目されるようになった背景には、今、日本の各地域で直面している暮らしや経済面での課題があります。
ここでは、地方の抱える課題や、時代の流れとともに変化した地方の価値について解説していきます。なぜ今、地方が投資先として注目されているのか、その理由についてひも解いていきましょう。
地方が抱える課題
地方創生が求められる背景には、長年にわたって積み重なってきたさまざまな地域課題があります。ここでは代表的な3つの課題、①人口減少、②空き家問題、③地域経済の衰退について整理します。
多くの地方では、若者が都市部に流出し、人口減少と高齢化が急速に進んでいます。
特に若年層の減少は深刻で、地域によっては学校の統廃合や、バス・電車などの公共交通の維持が難しくなるなど、日常生活にも大きな影響を及ぼしています。
国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」によると、2045年までに多くの地方自治体で人口が半分近くにまで減少する可能性があるとされています。
参考文献
人口減少の影響を最も象徴するのが、空き家の増加です。
総務省統計局が2023年10月1日に実施した「令和5年住宅・土地統計調査」の速報集計によると、全国の空き家数は約900万戸、空き家率は13.8%と報告されています。
空き家は、老朽化による倒壊リスクだけでなく、景観の悪化や防犯上の不安、地域コミュニティの衰退にもつながります。地方では、相続されたまま活用されず、誰にも管理されていない物件が特に目立ち、対策が急務となっています。
地方の多くはかつて、製造業や観光業、農林水産業など、地域に根ざした産業によって支えられてきました。
しかし、人口減少や大都市圏への一極集中の影響により、こうした産業の担い手が年々減少しています。その結果、商店街のシャッター通り化や雇用機会の減少が深刻化し、地域経済の衰退が加速しています。
地域内でお金や人の流れが滞ることで、地元で働き、暮らし、支え合うという地域の自立的な経済基盤が揺らいでいるのです。
コロナ禍で見直された「地方の価値」
そんな中、新型コロナウイルスの影響は、地方に対する人々の価値観を大きく変える転機となりました。
都市部の過密や通勤ストレスから解放されたいという想いから、「自然に囲まれた暮らし」や「人とのつながり」を求めて、地方移住や二拠点生活を検討する人が増えたのです。
また、テレワークの普及によって「どこで働くか」の選択肢が広がったことで、地方は「暮らす場所」として改めて注目されるようになりました。
地方は投資対象ではなく、未来の投資先に
かつて「地方=衰退する場所」と見られがちだった時代から、今や地方は新たな可能性を秘めた投資のエリアへと変わりつつあります。
地方にはまだ活用されていない魅力的な資源が多く残されており、空き家を活かした宿泊施設や、観光地の再生プロジェクトなど、投資によって地域がよみがえる事例も増えてきました。
さらに、国や自治体の支援制度や民間企業との連携が進むことで、投資リスクの軽減や出口戦略の確保も進んでいます。



単に「地方を応援する」というだけでなく、資産形成と社会貢献の両立を実現できる「未来の投資先」として、地方は改めて注目されているのです。
不動産クラウドファンディングで地方創生に貢献できる理由
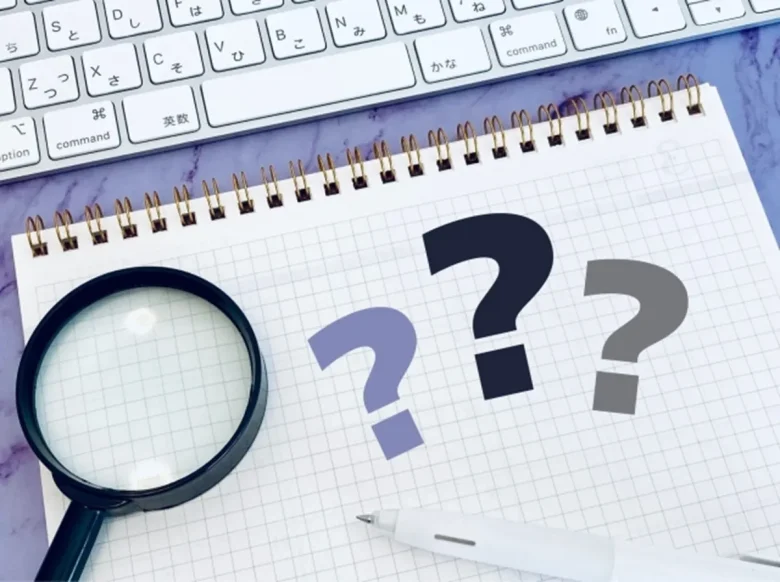
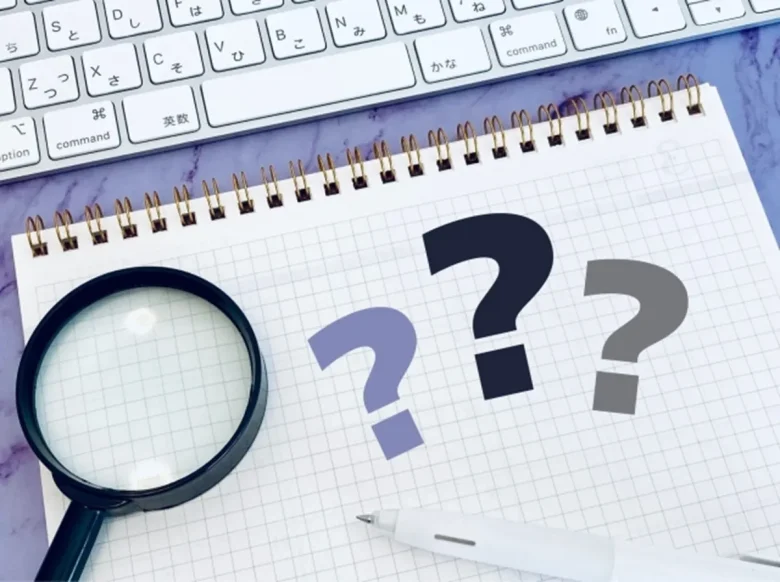
前述したとおり、地方にはまだ十分に活かされていない資源や可能性が多く眠っており、投資先としても注目が集まっています。
そんな、地方の魅力を活かす手段のひとつが、地方創生型の不動産クラウドファンディングです。なかでも、地域課題の解決を目的に企画された地方創生型ファンドや、エリアが地方にあることで地域経済にいい影響をもたらすファンドなど、地域と投資をつなぐプロジェクトが増えつつあります。
ここでは、実際に投資した資金がどのように地域に役立てられているのか、具体例とともにご紹介します。
投資資金が地域プロジェクトにどう生かされるのか
「地方創生型」のファンドでは、投資家から集めた資金が、空き家のリノベーションや観光施設の改修、地域施設の再整備などに活用され、地域に新しい価値や人の流れを生み出す取り組みにつながっています。
物理的に距離があっても、都市に住みながら地方のプロジェクトに関わることができるのは、不動産クラウドファンディングならではの魅力です。
【具体例】地方創生型ファンドとは?
では、実際にどのようなファンドが「地方創生型」とされているのでしょうか。
| 空き家再生ファンド | 築古の空き家をリノベーションし、宿泊施設や地域の交流拠点として再活用することで、地域に人の流れと新たな価値を生み出す。 |
| 観光再生ファンド | 老朽化した温泉旅館や観光施設を修繕し、観光資源の再活用と雇用創出につなげる。 |
| 商業施設活性化ファンド | シャッター街となった商店街の一角を再開発し、シェアオフィスや地元カフェなどとして活用し、地域の賑わいを取り戻す。 |
これらのファンドに共通しているのは、地域が抱える具体的な課題に向き合い、それを解決するという目的があることです。こうした事例は、空きスペースの活用がまち全体の再活性化につながるという好循環を生み出しています。
地方創生型ファンドの魅力と注意点


地方創生型ファンドは、投資を通じて空き家の再生や観光資源の活用などに貢献でき、他の投資商品にはない魅力を兼ね備えている点が特徴といえます。
一方で、他の投資商品と同様に注意しなければいけないポイントもあります。
そこで、ここでは地方創生型ファンドに投資する魅力と注意点についてご説明します。
高利回り案件が多い
地方立地の不動産は、立地リスクや流動性リスクがある分、投資家へのリターンが高めに設計される傾向があります。特に、再生によって資産価値を高めるプロジェクトでは、成功すれば都市部ファンド以上の利回りが期待できることもあります。
少しのリスクを取っても高いリターンを狙いたいという投資家にとっては、魅力的な選択肢となるでしょう。
プロジェクトの個別性が強く、見極めが重要
一方で注意すべきなのは、地方創生型ファンドは、案件ごとの差が大きいことです。対象物件の状態、立地、再生プランの現実性、運営会社のノウハウなどにより、プロジェクトの成功確率は大きく異なります。
「地方だから利回りが高い」という理由だけで選ぶのではなく、ファンドごとの内容をしっかり確認することが大切です。
売却や出口戦略に時間がかかる可能性がある
都市部と比べて不動産市場の規模が小さい地方では、ファンド終了後の売却先がすぐに見つからないこともあります。これにより、予定よりも運用期間が延びるリスクがある点には注意が必要です。特に、運用期間の延長リスクや売却益の可能性を理解した上で、事前にプロジェクトの出口設計が明確かどうかを確認しておくと安心でしょう。
・投資を通じて、社会や地域とのつながりを感じたい方
・中長期でじっくり投資に取り組みたい方
・少しリスクを取ってでも高利回りを狙いたい方
地方に投資するもう一つの方法


これまでご説明したとおり、不動産クラウドファンディングの中には、地域課題の解決を掲げる「地方創生型ファンド」が存在します。こうしたファンドは、社会的な意義が大きく、投資を通じてまちづくりに貢献できることが魅力です。
一方で、プロジェクトの個別性が強く、事業化の難易度や運用期間の長さなど、リスクが高めであることも事実です。そのため、興味はあるけれど自分には少し重いかもしれない、と感じる方もいるのではないでしょうか。そんな方にこそ知ってほしいのが、「立地が地方のファンドに投資する」という選択肢です。
地方創生型ではないが、地域への資金循環が生まれる
地方創生を目的にしていないファンドであっても、物件の立地が地方であれば、地域にお金の流れが生まれる可能性は十分にあります。
たとえば地方にあるホテルや賃貸マンションを対象物件とするファンドでは下記の効果が期待できます。
・建物の修繕や管理業務を地元の企業が担う
・稼働が上がることで、周辺の飲食店や観光施設への集客効果が生まれる
・施設の価値が維持されることで、地域全体の不動産価値が保たれ、波及効果によりその周辺の物件も注目されやすくなる。



地方創生型ファンドのように社会課題に直結していなくても、地域を静かに支える投資としての意味があるのです!
地域に関わるきっかけとして最適
都市部に住んでいても、どこかで地域との関わり方を模索している方は少なくありません。ただ、実際に移住したり、起業したりといった関わり方はハードルが高いものです。
そんな中で、地方物件を対象としているファンドへの投資は、無理のないかたちで地域とつながる最初の一歩になります。実際に投資することでそのまちに関心がわいたり、旅行や訪問のきっかけになったりすることもあります。
投資は、資産形成だけでなく地域との接点にもなるのです。
社会性とリスクのバランスをとれる投資スタイル
地方創生型ファンドは、社会的な意義が強く打ち出されている一方で、事業内容の特性上、リスクも高まりやすい傾向にあります。
それに対し、地方物件を対象としているファンドは、社会性とリスクのバランスがとれたちょうどよい投資商品となっているといえます。
・地方都市の中心部や観光需要の高いエリアが対象となっている
・実績のある会社が運営を手がけている
・安定稼働の実績がある物件が対象となっている



特に、これから初めて地方に投資してみたいと考える方にとっては、社会性とリターンのバランスが取れた選択肢として「地方物件を対象地しているファンド」は有力な選択肢となるのではないでしょうか。
Jointo αで始める、地方物件を対象としているファンドの魅力


ここまで、不動産クラウドファンディングにおける「地方創生型ファンド」の魅力と注意点、そして地方創生型ではなくとも「地方物件を対象としているファンド」というもうひとつの選択肢についてご紹介してきました。
ここからは、実際に地方に立地するファンドに投資できるサービスのひとつ、Jointo α(ジョイントアルファ)についてご紹介します。
地方エリアの良質な物件に投資できる
Jointo αでは、これまで全国各地から厳選した優良物件(マンションやホテルなど)を数多く取り扱ってきました。
都市部ではなかなか得られにくい高利回りの案件や、価格と価値のバランスに優れた物件を活用し、投資家にとっても地域にとってもメリットのあるスキームを構築しています。
地方エリアならではの不動産の魅力を活かしながら、安定稼働による収益性を両立できる点が、多くの投資家から支持されている理由のひとつです。
少額から始められて手間がかからない
Jointo αは、1口10万円から始められ、不動産投資が初めての方でも安心してスタートできる仕組みが整っています。
また、物件の管理や運用など、手間のかかる作業はすべて運営会社が担うため、忙しい会社員や家事・育児と両立した方にもぴったりのサービスです。
・煩雑な手続きや物件管理は一切不要
・スマホ1つで全て完結!時間や場所を選ばず投資が可能
運営会社の信頼性
地方の案件は、エリアによって売却に時間がかかったり、集客が不安定になったりといったリスクが想定されます。だからこそ、どんな運営会社がファンドを組成・管理しているかが非常に重要なポイントになります。
Jointo αを運営する穴吹興産株式会社が、マンション開発や賃貸管理など、全国で豊富な不動産実績をもつ東証スタンダード上場企業です。
長年にわたって地域に根ざした事業を展開しており、地方物件に対するノウハウや安定した運営体制が高く評価されています。
たとえ直接「地方創生」を掲げていなくても、信頼できる事業者が地域に投資し、その不動産を活用すること自体が、結果的に地域の活性化にもつながります。



「安心できる運営会社が手がけているかどうか」は、地方ファンド選びでの最も重要な判断軸のひとつです。
会員登録は無料!まずは情報収集から
Jointo αでは、無料会員登録をすることで、最新のファンド情報や募集スケジュールをいち早くチェックすることができます。
人気案件は、わずか数分で売り切れることもありまので、貴重なチャンスを逃さないためにも、事前に会員登録しておくことをおすすめします。
また、すぐに投資しなくても、サービスの雰囲気やプロジェクトの傾向を知っておくことで、自分に合ったタイミングで投資を始めやすくなります。
始めよう!不動産クラウドファンディング


不動産クラウドファンディングの中には、地域に関わることを目的としたファンドや、地方物件を対象とするファンドが数多くあります。
なかでも、空き家の再生や地域資源の活用など、地域課題の解決に取り組む「地方創生型ファンド」は、投資を通じて地方創生に貢献できる、社会的意義の高い選択肢として注目を集めています。
とはいえ、地方創生型ファンドは、プロジェクトの規模や内容によって難易度やリスクの幅が大きく、投資を検討するうえで、情報収集や判断に少し慎重さが求められる場面もあります。
いきなりは踏み出しにくいと感じる方へおすすめなのが、「地方物件を対象とするファンド」を通じて、間接的に地域を支えるという選択肢です。直接的に地方創生を掲げていなくても、地方の不動産に投資するという行動自体が、結果的にその地域の経済を動かす力になります。
たとえば、Jointo αのように地方エリアの優良物件に少額から投資できるサービスを活用すれば、無理なく、手間なく、そして静かに地域に関われるチャンスが広がります。
Jointo αの公式サイトでは、過去に取り扱ってきたファンド情報を確認することができます。まずは気になる物件やエリアからチェックしてみてはいかがでしょうか。
不動産クラウドファンディングと地方創生に関するよくある質問


【監修】


穴吹興産株式会社 不動産ソリューション事業部
アセットマネジメントグループ課長 穴吹 章彦
【資格】
・宅地建物取引士
・不動産証券化協会認定マスター
【経歴】
ソリューション事業部の業務に7年従事し、投資用不動産のアセットマネジメント業務を経験。現在は不動産特定共同事業におけるファンドの組成業務に従事し、投資家との契約業務全般を担当。不動産クラウドファンディングの仕組みや専門用語を解説しながら、情報発信を行っている。